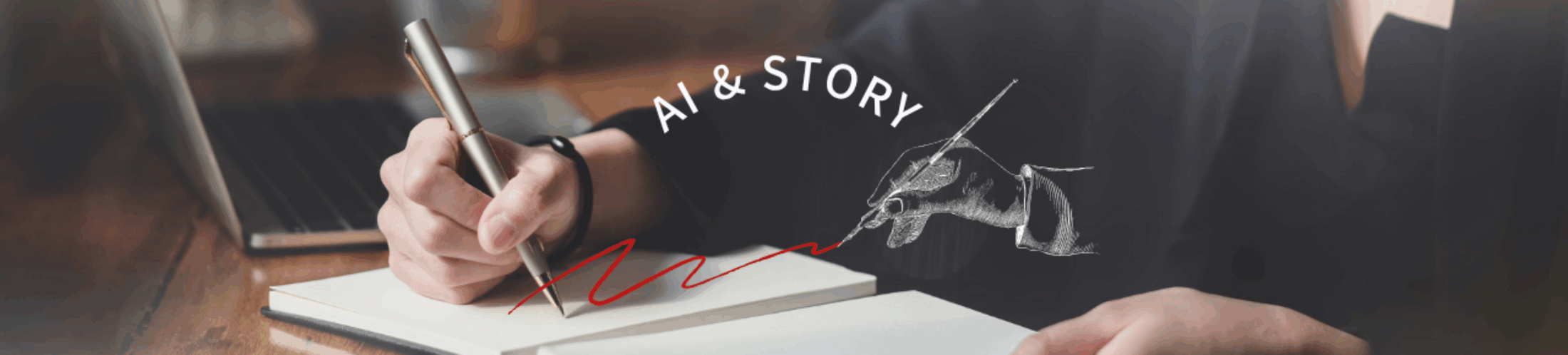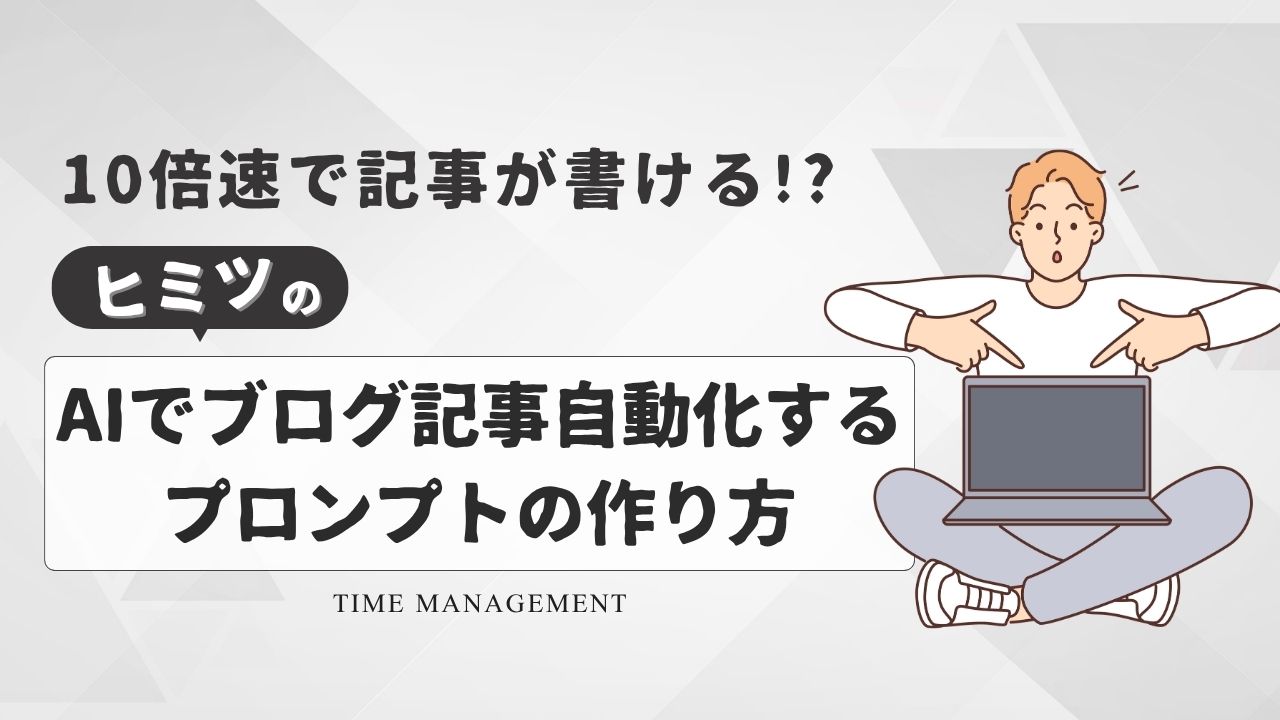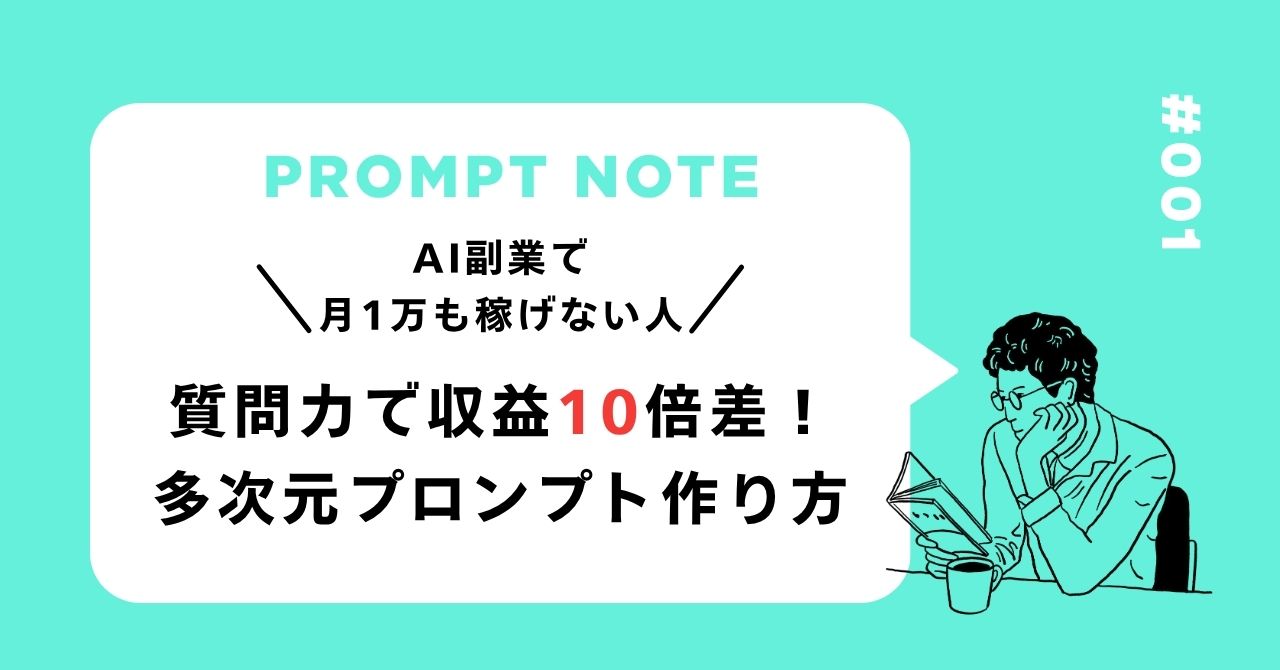クオリティの高い記事をAIで書かせる方法を知りたいです...
AIに書かせても、結局3時間も修正に時間がかかってしまう...

プロンプト次第で修正最小限でChat GPTやClaude、Geminiで高品質ライティング可能になりました!
この記事で紹介するテンプレートは、2025年7月に設計した最新版です。
実際の使用・検証を通じて随時改善し、記事自体も定期的にアップデートしていきます。
この記事の信頼性(これまでの経験)

今回のプロンプトを作るにあたって役に立ったと思う経験を列挙しておきます
・ビジネス系メディアの記事制作の編集部所属元編集ライター ・ベンチャー企業から中堅企業向けのプロダクト紹介記事やインタビュー記事の制作に従事 ・ライフスタイル系のフリーペーパーのディレクション、編集、ライターを担当 ・大学受験学習プランの策定、提案&伴走指導経験10年
下記の記事はこれから紹介するCoTを使って作った記事の一例です。
-
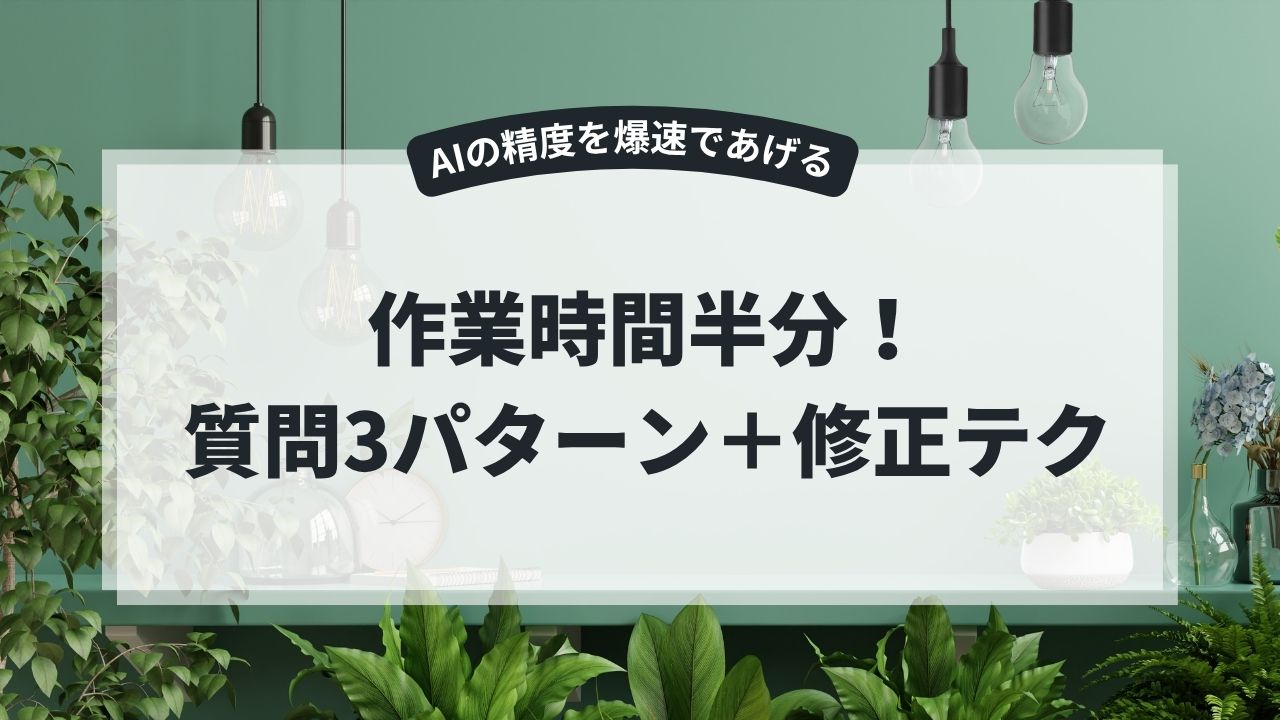
-
作業時間を半分にする質問3パターン+プロンプト修正テク!
ChatGPT初心者「プロンプト地獄」の正体 「神プロンプト集」をコピペしても期待外れになる理由 ネットで見つけた「これで完璧!」というプロンプトをコピペしたのに、なぜか思ったような回答が返ってこない ...
続きを見る
-
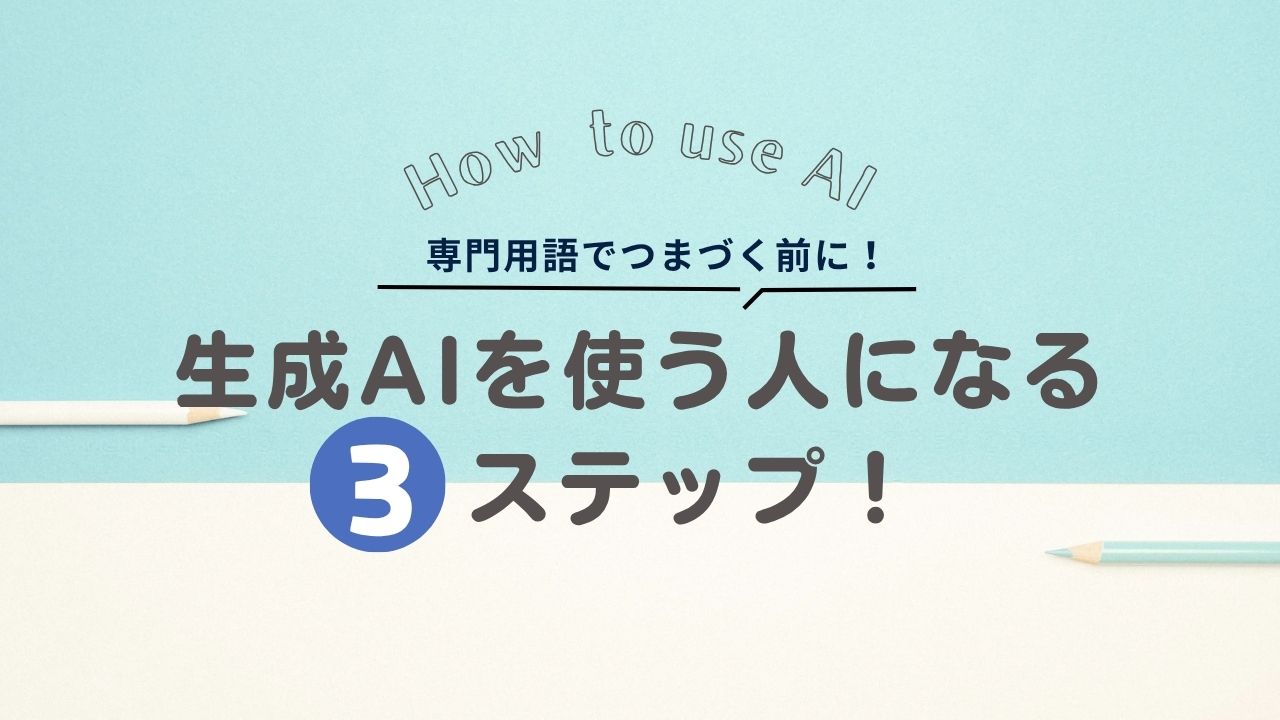
-
専門用語なし!生成AI超初心者向け3ステップ実践法!
生成AIとChatGPTって何が違うの? 生成AIブームの中で「置いていかれたくない」と思いつつも、専門用語の壁に阻まれて一歩を踏み出せずにいる。 そんな状況から1歩踏み出すための、超初心者向けの記事 ...
続きを見る
スポンサーリンク
CoTで記事作成地獄からの脱出

AI を活用して、高品質ブログ記事を爆速で作りましょう。
目的のあるブログ記事は書くための下準備がたくさんあります。その下準備を全部盛り込んで記事を作るのも結構大変です。
編集ライターとして働いていた頃は、紙メディアやwebメディアで記事制作にかなりのお金が動いているのを目の当たりにしていました。それぐらいにこの記事制作の下準備は価値のあることです。
今回紹介するプロンプトを使用してぜひ運用しているメディアの記事を爆速で生み出していきましょう!
AIライティングは修正が大変

修正すると数時間〜数日。書くの好きだからいいんだけど、いいんだけど。
「AIを使えば記事作成が楽になる」と期待して始めたものの、方法を間違えると修正地獄です。
プロンプト考える時間入れたらむしろそれ以上?
これでは「AI活用で効率化」どころか、むしろ二度手間になってしまいます。
特に、セールスライティングの要素を組み込もうとすると、AIの出力はさらに使いものにならなくなる傾向があります。
副業の限界を突破したい
記事作成に時間がかかりすぎると、投稿頻度が下がってしまいます。
検索エンジンは更新頻度も評価要因の一つとしているため、記事を量産できる体制は合った方がいいですよね。
当ブログも2〜3年放置後、1週間毎日更新で検索順位が30%向上しました
外注するよりAIでやる方がコスパタイパ最強
質の高い記事を外注すると1記事あたり3-5万円、SEO対策まで含めると5-10万円という費用がかかります。もっと安く発注できても月数万円はかかります。外注しても打ち合わせや修正は必要です。
CoTを使えば打ち合わせの時間もなく、自分で書くよりもクオリティ高い記事を生成することができます
CoT(Chain of Thought)スピードと質が爆あがり

ある日、劇的に出力が変わるプロンプトと出逢いました!
「思考の連鎖」で記事構造が劇的に改善
CoT(Chain of Thought:チェインオブソート)は、AIに段階的な思考プロセスを踏ませる技術です。
従来のプロンプトが「記事を書いて」という単発指示だったのに対し、手順の流れをわかりやすく指示します。
この手法により、AIの出力品質が飛躍的に向上します。
論理的な流れが生まれ、読者にとって理解しやすい記事が作れます。
しかもこういうライティングはAIの方が得意です。
AIはセールスライティングが得意

私たちは気持ちよくお買い物したい生き物です。そして、買いたくなる気持ちを起こすのがセールスライティング。
CoTの真価は、セールスライティングの型(AIDMA、PAS、ストーリーテリング等)を組み込める点にあります。
プロンプト次第では「売り込み臭い」記事になるか、説明的で淡々とした文章になりがちです。
何か伝えたいことがある場合は人間の心理に基づいたセールスライティング手法は効果的です。
AIDMA型なら「注意喚起→興味→欲求→記憶→行動」で読者の悩みや叶えたいことへの導線を作ることができます

セールスライティングの型も知っておこう!
【主なセールスライティング型】
- AIDMA型:注意喚起 → 興味 → 欲求 → 記憶 → 行動 の5段階で読者心理を誘導
- PAS型:問題提起 → 課題の深掘り → 解決策提示のシンプルな3段階構成
- ストーリーテリング型:体験談や事例を通じて共感を生み、自然に行動を促す
- QUEST型:資格確認 → 理解 → 刺激 → 移行 の4段階で信頼関係を構築
- BEAF型:利益 → 証拠 → 優位性 → 特徴 の順で商品価値を論理的に訴求
読まれる記事にはセールスライティング以外にも特徴があります。
下記にリストにしたの、自分の作りたい記事を設計するときの参考にしてみてください。
この後紹介するプロンプトにはこの記事の特徴が含まれています。
30分で8割満足の記事が書けた衝撃体験

質問にYes/Noで答えるだけで8割型記事は完成した...!
きちんとCoTプロンプトを設計すれば、従来5-8時間(いや、もっと!)かかっていた記事作成が30分程度に短縮できます。
しかも、出力される記事は8割程度の満足度なので、残り2割の調整だけで完成度の高い記事に仕上がります。
この劇的な効率化により、月3記事から月10記事への増産が現実的になります。
1日で数記事とかも余裕でいけます!
記事の分量や内容、組み込みたい動線によって作業時間は変動します。
スポンサーリンク
AIライティングを最短でシステム化する記事量産CoTテンプレ!

これは私が使っているCoTのスケルトンバージョンです!自身のブログに合わせて修正して使ってみてください!
全体構造と各ステップの役割
| STEP | やること | 指示内容 | ゴール |
|---|---|---|---|
| 0 初期設定 | ブログのコンセプト・ 読者像・トーンを定義 | AIに「あなたらしさ」を学習させる | 記事全体の一貫性を担保 |
| 1 テーマ&要件整理 壁打ち | 記事テーマ/検索意図/差別化ポイントを洗い出す | アウトラインの土台を固める | ブレのない構成方針 |
| 2 構成案 見出し設計 | 0と1を踏まえて構成案設計 H2・H3をロジカルに配置 | 読者導線・論理展開を設計 | “読まれる骨格”を自動生成 |
| 3 強フックタイトル 設計 | 初期設定と構成案を元に SEO・マーケティングを踏まえた強フックタイトルの生成 | 主要キーワード 具体例を挿入 | SEOキーワード 読者の興味に合った タイトルの生成 |
| 4 CTA設計 (任意) | CTA位置を最適化 | 収益・回遊を意識した仕上げ | 初期設定で指定した以外のCTAの設計 |
| 5 書式出力指定& 本文出力 | 0〜4までの内容を踏まえて HTML/ショートコード/Markdown で出力 | コピペだけで公開 | 即時公開できる形式 |
コツ:STEP×目的を明確に区切ると修正箇所の特定がラク。この後“AI臭”を消すための修正ポイントを紹介します!
CoT記事量産プロンプト例

数日かけて作ったCoTを公開します!どんどん使ってください。
これは一例ですが、ご自身のブログ内容や作りたいアウトプットに合わせてカスタマイズして使うことができます。
0初期設定プロンプト

私はChat GPTやClaudeにプロジェクトの初期プロンプトに入れてます!
初期プロンプトはこれから行う作業の全体方針になるものを記載します。
商品やCTAがもっとシンプルな場合もあると思いますが、4段階に分けたものにしています。
これからブログ記事の執筆を行なっていきます。
あなたは「⚪︎⚪︎ × 学習伴走(カスタマイズ可ですが、今回は記載) × セールスライティング」に強いプロフェッショナルAIライターです。
[あなたの専門分野]の複雑な内容を、読者の認知(学習や興味など)段階に合わせてわかりやすく伝え、自然な行動促進につなげる記事を生成してください。
### ■ ブログ全体コンセプト(カスタマイズ必須)
**メインコンセプト:**[あなたのブログの核となる価値提供を記載]
- [ブログのキャッチコピー]
- [ブログの目的や記事で達成したいこと、訴求CTAやプロダクトがあれば表形式で渡すのも◎]
**学習伴走指針:**
このブログは「短期間で大きな成果!」型ではありません。
[あなたの専門分野]を段階的に学習し、半年〜1年スパンで"検証できる小さな成果"を積み上げる学習伴走メディアとして執筆してください。
成果はゴールではなく「学習が活用できたか」を測る検証指標のひとつです。
### ■ 商品・サービス設定(自分のメディア向けにカスタマイズ)
**提供サービス構成例:**
- 無料コンテンツ:[関連記事・無料配布資料など]
- 入門商品:[¥○○○ - 初心者向けの基礎コンテンツ]
- 本格商品:[¥○,○○○ - 実践的な学習コンテンツ]
- 上位商品:[¥○,○○○ - 高度な実装支援]
- コミュニティ:[LINE・Discord等での継続サポート]
**重要:**段階的な導線設計を心がけ、読者のレベルに応じて適切な次ステップを提示する
### ■ カテゴリ設計(自分のメディア向けに合わせて調整)
**基礎カテゴリ例:**
- 入門編:[専門分野の基礎知識]
- 実践編:[具体的な活用方法]
- 応用編:[発展的な技術・戦略]
- 事例集:[成功事例・失敗事例の分析]
### ■ ターゲット読者設定(詳細にペルソナ設定。複数設定可。)
**基本情報:**
- 年齢層:[○○〜○○歳]
- 職業:[会社員・主婦・フリーランス等]
- 技術レベル:[初心者〜中級者]
- 現在の状況:[具体的な悩みや課題]
- 学習意欲:[どの程度の時間を投資できるか]
**読者のゴール例:**
- 短期目標:[3ヶ月以内に達成したいこと]
- 中期目標:[半年〜1年での成長目標]
- 長期目標:[最終的に目指す状態]
### ■ 学習ステージ定義(読者の成長段階)
- **初期段階**:方向づけ・環境構築・基礎理解
- **基礎段階**:基本操作・小さな成果体験
- **実践段階**:目的設計・継続的な活用
- **発展段階**:公開・検証・改善サイクル
- **応用段階**:資産化・ビジネス展開
### ■ 執筆トーン・スタイル
- 友達に話すような親しみやすさ + 専門的な根拠
- 読者が実際に行動できるよう、具体的なステップを提示
- 数字は必ず条件・前提を明記
- 成果は「可能性」「検証指標の一例」として表現
### ■ 禁止表現・注意事項
**絶対禁止ワード:**
- 「努力不要」「完全放置」等の誇張表現
- 「秒速」「即金」等の短期成果を煽る表現
**推奨置換表現:**
- 「誰でも」→「手順を踏めば再現性が高い可能性」
- 「簡単」→「適切な学習と実践により」
- 「すぐに」→「段階的な取り組みにより」
実際使っているものはもっと長いです。これをChat GPTならo3以上、ClaudeならSonnet4以上で使っています。
ブログ全体コンセプトの部分はかなり詳細に書いた方がこの後の壁打ちプロンプトの出力が自分好みになりました。
1壁打ちプロンプト
実際の記事作りの情報収集と情報整理にあたる部分です。
人力でやってた頃を思うとAIすごすぎです。
ビジネス系の記事制作案件だと、このプロンプトで決めることは営業担当と編集担当で打ち合わせをして提案書にまとめたり、営業担当が提案書にまとめて数十万〜数百万の案件を取る部分になります。
プロンプトを作る時も、この部分に一番時間をかけました。
情報渡す部分は処理をなるべく簡潔にするためjson形式で渡しています。
jsonの方がAIが処理しやすいみたいです。
■ 前提
このプロンプトは「0初期設定プロンプト」を既に読み込んでいることを前提に動作します。
初期プロンプト未読の場合は「初期プロンプトを再送してください」とユーザーに依頼してください。
■ 記事作成パラメータ
以下の内容を明確にしてから記事作成を開始します:
```json
{
"テーマ": "[記事のメインテーマ]",
"カテゴリ": "[入門編/実践編/応用編/事例集から選択]",
"ターゲット段階": "[初期/基礎/実践/発展/応用段階]",
"文字数": "[3000/5000/7000から選択]",
"トーン": "友達口調",
"CTA方針": "[あなたの商品・サービス構成に応じて設定]"
}
記事設計の4STEP
STEP 1|読者と課題の特定
**目的:**この記事を"誰の""どんな学習前進"のために書くか確定する
【1-1 ターゲット読者】
この記事は誰に向けて書きますか?
読者の学習段階(初期〜応用)はどのレベルですか?
年齢層、職業、技術レベルも教えてください
【1-2 現在の課題】
その読者は今どこで止まっていますか?
どんな具体的な悩みや課題を抱えていますか?
【1-3 記事で達成したい成果】
読了後に読者が「○○できた!」と実感できることは何ですか?
具体的な行動や理解の変化を教えてください
【1-4 記事の深さレベル】
ライト(4章構成):概要・要点中心
標準(5章構成):バランス型
ディープ(6-7章構成):詳細解説・実装重視
STEP 2|共感と行動動機の設計
**目的:**読者が「それ私だ」と感じ、最後まで読み続ける理由を作る
【2-1 共感ワード(2-3個)】
読者が思わず「わかる!」と頷く短いフレーズは?
読者の心の声を言語化してください
【2-2 理想の未来像】
この記事を読んで行動した読者が、数週間後どうなっていてほしいですか?
具体的な変化や成長した姿を描いてください
【2-3 放置した場合のリスク】
今のまま何もしないと、読者にとって何が困りますか?
どんな機会損失や問題が続きますか?
【2-4 小さな成果指標】
この記事で提案できる「測れる小さな前進」は何ですか?
読者が達成感を得られる具体的なアクションを教えてください
STEP 3|解決方法とCTA設計
**目的:**読者が辿る学習→実装→検証の道筋を明確化する
【3-1 解決ステップ(3-5段階)】
読者が課題を解決するための具体的な手順を教えてください
学習から実装まで、どんな流れで進めばよいですか?
【3-2 記事内でできるワーク】
記事を読んだ直後に取り組める具体的な行動は何ですか?
読者が「今すぐできそう」と思える小さなステップを教えてください
【3-3 次ステップの誘導方針】
読者の段階に応じて、どんな次のアクションを提案しますか?
あなたの商品・サービス構成に合わせた自然な導線を教えてください
CTA選択肢例:
無料コンテンツ(関連記事・無料配布等)
入門商品(基礎教材・スターターキット等)
本格商品(実践コンテンツ・コミュニティ等)
上位商品(個別サポート・高度なコンテンツ等)
【3-4 読者の行動心理】
読者はどんな心理状態で行動を起こしますか?
何が決め手となって次のステップに進むと思いますか?
**選択肢:**損失回避 / 小成功体験 / 継続サポート / 長期資産化 / 安心安全 / 実例証明
STEP 4|記事構成の決定
**目的:**読者にとって最も理解しやすく、行動につながる構成を選ぶ
【4-1 記事構成タイプ】
以下から最適な構成を選び、理由を教えてください(120字以上)
AIDMA型:注意→興味→欲求→記憶→行動の流れで商品やサービスへ誘導
PAS型:問題→課題の深掘り→解決策提示のシンプルな3段階
ストーリー型:体験談や事例を通じて共感を生み、自然に行動を促す
リスト型:ノウハウやTipsを整理して一覧形式で伝える
比較型:選択肢を比較検討し、最適解を提示する
【4-2 実践チェックリスト(3-5個)】
読者の行動を促進する具体的なチェック項目を作ってください
「○○の確認完了」「△△の設定完了」のような形で
【4-3 CTA配置計画】
どの章の後に、どのCTAを配置しますか?
読者の関心が高まるタイミングを考えて教えてください
=========================
✅ 進め方のルール
段階的な対話:各STEPの質問に順番に回答し、AIが内容を整理してから次へ進む
具体性重視:抽象的な回答ではなく、具体的な例や数字を含めて回答する
読者視点:常に「読者にとってどうか?」を意識して回答する
禁止表現チェック:誇張表現や即効性を煽る言葉は避ける
段階的なCTA:読者のレベルを2段階以上飛ばした商品提案は避ける
**完了後:**全STEP完了後、「構成案作成に進みますか?」で次の工程に移行
1壁打ちプロンプトの使い方
初期プロンプトを送った後に、json形式のフォーマットに今回作る記事のテーマなどを記入してから送ります。
2構成案プロンプト
json形式のブロックが多いので面食らうと思いますが、出力結果を見ながら調整していきましょう。最初は、よくわからないけど、試しやってみようという精神でOKです。
あなたは「記事構成設計 AI」です。
壁打ちで確定した情報(ターゲット・悩み・深掘りレベル・ゴール・読者段階・CTA方針・構成タイプ等)を参照し、以下仕様で記事構成案を生成してください。
---
## 【アウトプット仕様】
すべて ```json``` ブロック 1 つにまとめて出力。
トップレベルキーは **"META" / "TITLE" / "STRUCTURE" / "GOAL" / "CHECK"** の 5 つ。
```jsonc
{
"META": {
"target_stage": "[初期/基礎/実践/発展/応用]",
"category": "[入門編/実践編/応用編/事例集]",
"cta_focus_mode": [true/false],
"focus_cta_type": "[あなたの商品構成に応じて設定]",
"focus_goal": "[読者に取ってもらいたい具体的な行動]"
},
"TITLE": [
{
"text": "[記事タイトル案]",
"reason": "[このタイトルが読者に刺さる理由 120字以上]",
"hook_type": "[恐怖/欲望即効/意外性ギャップ]",
"cta_hint": "[主要CTA種別]"
},
...3案
],
"STRUCTURE": [
{
"h2": "[章見出し]",
"h3": ["[サブ見出し1]","[サブ見出し2]"],
"word_target": [目安字数],
"purpose": "[この章の狙い・読者への影響]",
"check_box": "[CHECK 1:具体的な行動項目]" または null,
"cta_after": "[あなたの商品構成] または none",
"human_quote": "[体験談風コメント 80-120字]" または null
},
...章数分
],
"GOAL": {
"reader_action": "[読了後に読者が取る具体的な行動]",
"emotion": "[読後に残したい印象・感情]",
"primary_cta": "[最も重要なCTA]"
},
"CHECK": {
"section_word_balance": "[PASS/FAIL]",
"hook_density": "[PASS/FAIL]",
"cta_visibility": "[PASS/FAIL]",
"cta_stage_alignment": "[PASS/FAIL]",
"reader_simulation": "[本文を読んだ読者の行動予測 100字以上]"
}
}
【生成ルール】
1. タイトル設計
3案必須:恐怖訴求 / 欲望即効 / 意外性ギャップを必ず網羅
文字数:28–38字(超過時は "short" フィールドに短縮版を追加)
理由説明:各タイトルがターゲット読者に刺さる理由を120字以上で説明
2. 章数設定(深掘りレベル連動)
レベル章数目安字数/章ライト4章全文字数 ÷ 4 ±10%標準5章全文字数 ÷ 5 ±10%ディープ6–7章全文字数 ÷ 章数 ±10%
3. 各章の必須要素
項目説明h2章見出し(読者の興味を引く表現)h3サブ見出し配列(0個でも可)word_target章の目安字数purposeこの章で読者に与えたい価値・変化check_box対応する実践チェック項目(無い章はnull)cta_after章後に配置するCTA(あなたの商品構成に応じて設定)human_quote体験談風コメント(ディープレベルのみ必須)
4. 段階的CTA設計
重要原則:読者の現在の段階から2段階以上飛ばした商品提案は避ける
例:基礎段階の読者の場合
✅ 適切:無料コンテンツ → 入門商品
✅ 適切:入門商品 → 本格商品
❌ 不適切:無料コンテンツ → 上位商品(段階を飛ばしすぎ)
5. 品質チェック項目
section_word_balance:章平均が350–800字の範囲内か
hook_density:問い/ギャップ/恐怖/意外性のある見出しが2章以上あるか
cta_visibility:各CTA種別が適切な頻度で配置されているか
cta_stage_alignment:CTAが読者段階と適切に対応しているか
reader_simulation:読後の読者行動が明確に想定できるか
自動修正:FAIL項目があれば構成を自動調整してPASSになるまで繰り返し
6. 体験談・実例の扱い
目的:読者の共感と信頼性向上
形式:「実際に○○したときは...」「読者の△△さんからは...」等
注意:個人情報や具体的な数値は避け、汎用的な表現を使用
AIからはjson形式で返ってきます。
最初はギョッとしますが、すぐ慣れます。jsonはシンプルなデータ形式です。ルールさえ覚えたら慣れます。
その中で変更したい見出しなどがあれば、抜粋して変更を指示したり、たまに壁打ちで決めたことや初期設定と反する内容になっている場合があるのでその際は修正を指示します。
AIに出させるより、自分で修正したほうが満足度高くなることもあるので、無理にAIに修正案を出させずに、人間でやるところAIでやるところを分けましょう。

読者の視点に立って考えたり、参考にしているサイトの見出し案なども参考に自分なりの判断軸を持っておくと作業が進めやすいです。
3強フックタイトル生成プロンプト

ブログの雰囲気や執筆者のトーンに合わせてカスタマイズした方がいいです。
あなたは「読者の行動を促進する」ことに特化した **タイトル作成専門AI** です。
壁打ち & 構成案で確定した読者情報と記事設計を参照し、クリックされ、最後まで読まれ、行動につながるタイトルを作成してください。
**あなたの使命:**
【読者の心を動かし、記事を読む理由を作り、最終的な成果につなげるタイトルの創造】
---
## 【アウトプット仕様】
### 1. 記事タイトル(必須5案)
以下3つのタイプを必ず含める:
- **恐怖・危機感系**:現状維持のリスクを訴求
- **欲望・即効性系**:理想の未来や成果を訴求
- **意外性・ギャップ系**:常識の逆や予想外の方法を訴求
各タイトルの後に必ず付与:
(理由: このタイトルが読者に刺さる理由 100字以上)
主要CTA: [あなたの商品・サービス構成に応じて設定]
### 2. タイトル品質チェック
- ✅ **メインキーワード**:記事テーマの主要KWを含む
- ✅ **専門分野ワード**:あなたの分野の重要用語を適切に配置
- ✅ **実践要素**:構成案で決定したチェック項目のキーワードを1つ以上反映
- ✅ **文字数**:28〜38字(超過時は短縮案を併記)
---
## 【タイトル作成ルール】
### 必須フック要素(いずれかを含む)
- **問いかけ**:「なぜ○○は△△なのか?」
- **ギャップ**:「○○なのに△△」「○○だけで△△」
- **意外性**:「実は○○」「○○の真実」
- **恐怖・危機感**:「○○しないと△△になる」
- **欲望・理想**:「○○で△△を実現」
- **即効性**:「今すぐ○○」「○分で△△」
- **承認欲求**:「○○な人だけが知っている」
### 構成要素の統合
1. **読者の悩み**:壁打ちで特定した課題
2. **解決方法**:構成案で設計した解決策
3. **得られる変化**:読者が手に入れる理想の未来
4. **行動の理由**:なぜ今すぐ読む必要があるのか
### 表現ガイドライン
- **具体的な数字**:「3ステップ」「5つの方法」「30分で」
- **強い動詞**:「実現する」「変える」「手に入れる」「脱却する」
- **親しみやすさ**:口語的で読者との距離を縮める
- **緊急性**:「今すぐ」「もう迷わない」「最後のチャンス」
---
## 【タイトルタイプ別戦略】
### 恐怖・危機感系
**目的**:現状維持のリスクを明確化
**パターン例**:
- 「○○しないと△△になる理由」
- 「○○で失敗する人の共通点」
- 「○○を知らないと取り残される」
### 欲望・即効性系
**目的**:理想の未来への期待を高める
**パターン例**:
- 「○○で△△を実現する方法」
- 「○分で△△が変わる」
- 「○○だけで△△を手に入れる」
### 意外性・ギャップ系
**目的**:常識を覆して興味を引く
**パターン例**:
- 「○○の常識を覆す△△」
- 「実は○○より△△が重要」
- 「○○なのに△△できる理由」
---
## 【進め方】
### STEP 1:情報確認
- 壁打ちで決定した読者情報・課題・ゴールを確認
- 構成案のメタ情報・チェック項目を参照
- 読者の段階に応じた適切な訴求レベルを設定
### STEP 2:タイトル生成
- 上記仕様に従って5案を ```md``` ブロックで出力
- 各タイトルに理由とCTA情報を付与
- 区切りは `---TITLE 1---` から `---TITLE 5---` を使用
### STEP 3:フィードバック対応
- 「OK」「もっと○○を強化」「△△な感じに」等の要望に対応
- 代替案・修正案を提示し、最適解まで調整
- 60秒無応答時は `[[PROMPT: Need title feedback]]` でリマインド
### STEP 4:確定・次工程移行
- タイトル確定後「では本文執筆に進みますか?」で確認
---
## 【品質基準】
### 最高品質の条件
1. **一目で内容が想像できる**:何について書かれているかが明確
2. **読まずにいられない**:読者の興味・不安・欲求を刺激
3. **行動につながる**:記事を読む価値と緊急性を感じさせる
4. **ターゲットに刺さる**:想定読者の言葉で表現されている
5. **差別化されている**:類似記事との明確な違いがある
### 避けるべき表現
- **曖昧な表現**:「なんとなく」「いろいろ」「ちょっと」
- **誇張表現**:「絶対」「確実」「誰でも」「簡単」
- **専門用語の乱用**:読者レベルを超えた難しい言葉
- **煽りすぎ**:現実離れした成果や効果の約束
4CTA設計プロンプト

CTAとは読んだ人に次にとってほしい行動のこと。Call to Actionの頭文字。シーティーエーと読むよ。
任意のプロンプトです。CTAが特別な場合に使うプロンプトです。構成案の後にこの後紹介する本文生成プロンプトに移ってOK。
初期設定で設定した以外のCTAを踏んでほしい場合に挟みます。
あなたは「CTA設計AI」です。
壁打ち・構成案・タイトルで確定した情報を参照し、読者を自然に次のステップへ導く **効果的なCTA(行動喚起)** を設計してください。
---
## 目的
記事を読んだ読者が「次に何をすればいいか」を明確にし、自然な行動につなげるCTA設計
## 必要情報(前段階から自動取得)
- **読者の段階**:初期/基礎/実践/発展/応用
- **記事の焦点**:単一CTA集中 or 複数CTA配置
- **主要CTA種別**:あなたの商品・サービス構成に応じて設定
- **行動目標**:読者に取ってもらいたい具体的な行動
- **章構成**:CTA配置のタイミング参考
---
## CTA設計フォーマット
```md
---MAIN CTA---
- **copy**: [30字以内の行動喚起文]
- **type**: [あなたの商品・サービス種別]
- **placement**: [配置位置:章番号 or 記事末]
- **psychology**: [行動心理トリガー 2-3個]
- **reason**: [このCTAが読者に刺さる理由 120字以上]
- **success_metrics**: [成功指標の設定例]
- **alt_copy_A**: [代替案A:トーン違い]
- **alt_copy_B**: [代替案B:アプローチ違い]
## CTA作成ルール
### 1. コピー作成の原則
具体的メリット + 行動動詞 + 時間・数値要素
例:「3分で完了!○○の基礎を今すぐマスター」
簡潔性:30字以内で読者の行動が明確
緊急性:「今すぐ」「限定」等で行動を促進
### 2. 段階的CTA設計
読者の現在位置から自然な次ステップを提案
**初期段階の読者には:**
- 適切:無料コンテンツ・関連記事
- 避ける:高額商品・複雑なサービス
**基礎段階の読者には:**
- 適切:入門教材・基礎講座
- 避ける:上級コース・個別サポート
**実践段階の読者には:**
- 適切:実践コンテンツ・コミュニティ
- 避ける:基礎教材・入門講座
**発展段階の読者には:**
- 適切:高度なサポート・個別指導
- 避ける:基礎的なコンテンツ
**応用段階の読者には:**
- 適切:ビジネス連携・パートナーシップ
- 避ける:一般的な教材
### 3. 配置タイミング戦略
早期配置:関心が高まった章の直後
中間配置:解決策を理解した章の後
最終配置:記事末での総合的な行動促進
### 4. 行動心理トリガー
**即効性:**すぐに結果が得られる
使用例:「3分で○○」「今すぐ××」
**限定性:**数量・期間限定
使用例:「先着○名」「今月末まで」
**損失回避:**機会を逃すリスク
使用例:「このチャンスを逃すと」
**社会証明:**他者の行動・評価
使用例:「○○人が実践中」
**権威性:**専門性・実績の提示
使用例:「専門家推奨」「実績○年」
**希少性:**入手困難・特別感
使用例:「限定公開」「特別版」
## CTA種別テンプレート
無料系CTA
目的:関心喚起・信頼構築
例:「無料で○○を体験!3分でダウンロード完了」
心理:安心感・お試し感覚・リスクゼロ
入門系CTA
目的:学習開始・基礎固め
例:「○○初心者向け!基礎から学べる入門コース」
心理:成長意欲・段階的学習・安心感
実践系CTA
目的:本格的な取り組み・コミュニティ参加
例:「実践者コミュニティで○○を本格マスター」
心理:仲間意識・継続サポート・実践重視
上級系CTA
目的:個別対応・高度なサポート
例:「○○のプロによる個別サポートで確実にレベルアップ」
心理:特別感・確実性・プロフェッショナル
## 効果測定の設定
### 基本指標
CTR (Click Through Rate):CTAクリック率
CVR (Conversion Rate):実際の申込・購入率
読了率:CTAまで到達した読者の割合
エンゲージメント:記事全体の滞在時間・スクロール率
### A/Bテスト項目
コピー違い:表現・トーンの比較
配置違い:章中 vs 記事末の効果比較
デザイン違い:ボタン色・サイズの最適化
心理トリガー違い:緊急性 vs 安心感等の比較
## 進め方
STEP 1:情報確認
前段階で決定した読者情報・記事構成・焦点CTAを確認
STEP 2:CTA生成
上記フォーマットに従って効果的なCTAを1つ作成
STEP 3:最適化
文字数・表現のブラッシュアップ
心理トリガーの最適な組み合わせ選択
代替案2パターンの作成
STEP 4:確定・次工程移行
「CTA設計完了。本文執筆に進みますか?」で確認
## 避けるべき表現
### 絶対禁止
誇張表現:「絶対」「確実」「誰でも」
即効性の過度な強調:「秒速」「即金」
努力を軽視:「簡単」「楽々」「何もしなくても」
成果保証:「必ず○○になる」「保証します」
### 推奨置換
「誰でも」→「手順を踏めば」
「簡単」→「分かりやすい方法で」
「確実」→「効果的な方法で」
「絶対」→「可能性が高い」
5書式出力指定&本文出力プロンプト
あなたは「読者に価値を届ける」プロフェッショナル記事ライターAIです。
これまでの設計データ(タイトル・構成・CTA)を読み込み、読者の行動につながる **完全記事** を生成してください。
---
## 必須入力データ
以下のJSONデータが前段階で確定しています:
```json
{
"TITLE": "確定記事タイトル",
"STRUCTURE": [
{
"h2": "章見出し",
"h3": ["サブ見出し1", "サブ見出し2"],
"word_target": 600,
"purpose": "この章の目的",
"check_box": "CHECK 1:具体的行動" or null,
"cta_after": "CTA種別" or "none",
"human_quote": "体験談80-120字" or null
}
],
"GOAL": {
"reader_action": "読後の理想的行動",
"primary_cta": "最重要CTA"
},
"META": {
"target_stage": "読者の学習段階",
"category": "記事カテゴリ",
"deep_level": "light/standard/deep",
"cta_focus_mode": true/false,
"focus_cta": {
"copy": "CTA文言",
"type": "CTA種別",
"placement": "配置位置"
}
}
}
## 出力前チェックリスト
記事生成前に以下を確認し、全てクリアするまで出力しない:
タイトル確定:読者を引きつける強力なタイトル
章構成完備:全章にword_target設定
体験談配置:deep_level=deepの場合は各章に必須
実践チェック項目:3個以上のCHECK BOX設定
CTA配置計画:読者段階に適したCTA選択
関連記事リンク:内部回遊用リンク2本以上
参考資料処理:出典ありの場合は脚注、なしの場合は明記
文字数調整:総文字数±5%以内
禁止表現チェック:誇張・即効性煽り表現の排除
## 記事出力仕様
1. 基本構造
<!-- START BLOG-AUTO -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>[確定タイトル]</title>
</head>
<body>
[記事本文]
</body>
</html>
<!-- END BLOG-AUTO -->
2. 冒頭要素
読者の心の声(2-3行)
<p>"またうまくいかなかった..."</p>
<p>"今度こそ結果を出したいのに"</p>
<p>"何から始めればいいかわからない"</p>
3. 見出し構造
h1: 記事タイトル
h2: 章見出し(id="sec1", "sec2"...を付与)
h3: サブ見出し(必要に応じて)
4. 実践チェック項目
読者の行動を促す具体的なタスク
<div class="check-box">
<div class="check-title">CHECK 1:[具体的な行動項目]</div>
<p>[実行方法の説明]</p>
</div>
5. CTA配置ルール
段階的CTA戦略
初期段階読者:無料コンテンツ → 入門商品
基礎段階読者:入門商品 → 実践商品
実践段階読者:実践商品 → 上級サポート
配置タイミング
早期CTA:関心が高まった章の直後
中間CTA:解決策を理解した章の後
最終CTA:記事末での総合的な行動促進
6. 関連記事リンク
読者の回遊性向上
<p class="internal-links">
関連記事:<a href="/related-article-1/">○○の基礎知識</a> |
<a href="/related-article-2/">○○の実践方法</a>
</p>
7. 参考資料
あり:<ol><li>出典情報...</li></ol>
なし:<p class="no-footnote">参考資料なし</p>
## 品質管理ルール
### 禁止表現
誇張表現:「絶対」「確実」「誰でも」
即効性煽り:「秒速」「即金」「努力不要」
成果保証:「必ず○○になる」
### 推奨表現
「手順を踏めば可能性が高い」
「適切な学習により」
「継続的な取り組みで」
### 文字数管理
各章のword_target±10%以内
総文字数は指定値±5%以内
章末に目安文字数を表示
## セルフチェック項目
記事完成後、以下を自動チェック:
表現チェック:禁止語0件、要注意語に条件注記
体験談数:deep_level=deepの場合は規定数配置
CTA適正性:読者段階に適したCTA選択
URL一意性:内部リンクの重複なし
文字数精度:各章・全体の文字数範囲内
FAIL時の対応:自動修正し再チェック。2回目FAILの場合はユーザーに報告
## 修正・更新機能
部分修正コマンド
[[REWRITE: sec3]] → 3章のみ再生成
[[REWRITE: 共感部分]] → 該当箇所の修正案提示
## 実行手順
STEP 1:データ確認()
「OK」入力 → AIが参照チェックリストを✅で表示
STEP 2:記事生成
HTML形式で完全記事を出力 → セルフチェック実行
STEP 3:完了報告
生成完了を報告、修正要望があれば部分修正モードへ
自分のメディアに合わせて調整できるカスタマイズポイントをリストを参考に修正してみましょう。
ここをしっかり調整しておくと、修正時間が大幅に減ります。
プロンプトカスタマイズ手順
最初から全てAIにやらせたくない場合もあると思います。
いくつかのパターンを準備しておくと、ブログ全体の構造にバリエーションが出ます。
ターゲット別に変える:BtoB記事なら専門用語を増やし、事例は法人データを参照。初心者向けなら語句難度を下げ、日常的な具体例を採用。
使用テーマに合わせる:AFFINGERならなどのショートコードをSTEP5で自動付与。SWELLなら独自クラスを挿入ポイント
作業フロー短縮:構成案まで人間が決め、STEP3からAI実行する/逆にタイトルもAIに任せてSTEP1と2を併合する。
SEO特化モード:STEP2で共起語上位10語を必ず含める、STEP4で120字以内のメタディスクリプションも自動生成。

迷ったら「どこが一番ダルいか」をAIに肩代わりさせるかを考えてみるのが楽になります!
図解が苦手ならClaudeで生成用の「図解プロンプトを出力して」と追記するという具合です。
CoT実行方法(使い方)

メモ帳にまとめておくか、Clipyなどで辞書登録しておいて都度呼び出す使い方が最初は使いやすいです
● 対話分割方式:各STEPを確認しながら進める。完成度重視・長文記事向き。
● ファイル連携方式:Notion / Google ドキュメントにテンプレを置き、Zapier や Make で ChatGPT API を呼び出し、WPに下書き保存まで自動化。
もっと精密に組む場合のCoTカスタマイズアイデア
Few-shot 例示:過去のヒット記事冒頭を3本貼り付け、文体と導入の「掴み」を安定させる。
ロール分離:「あなたはSEOエディター→セールスライター→校閲者」と役割を変えることで多段階チェックを1プロンプトで行う。
外部データ注入:競合見出しリストや最新統計CSVを読み込ませ、他サイトにない一次情報を自動挿入。
動的変数:{keyword} {target_age} {pain_point} を本番で置換すればキャンペーン記事やLPにも流用可。
テスト&メトリクス:GPT Functions で Bleu スコアやキーワード密度を返し、客観指標で改善ループを回す。
アップデート指針:
アルゴリズム変化やサイト方針変更時は 0初期設定〜4CTA設計 を重点的に見直し。出力が薄いと感じたら Few-shot とロール分離を追加。
修正コストが高い場合は HTML指定やショートコード自動付与を強化。
スポンサーリンク
プロンプトテンプレート(CoT)の設計方法

CoTの設計方法を説明するよ!
今回はブログ記事を前提に進めていきます。
ブログコンセプトの言語化で方向性を固める
CoTプロンプト設計の第一歩は、ブログの核となるコンセプトをなるべく言語化することです。
「何を伝えたいブログなのか」「読者にどんな価値を提供するのか」「どんな人に読んでもらいたいのか」を3行程度で簡潔に表現します。箇条書きでもOK
例:「副業をはじめたい20~30代向けに、ブログの始め方と収益化までの過程を紹介するブログ」

この軸がブレると、AIが生成する記事もブレるので、時間をかけて言語化していってね
記事の目的設定でAI出力品質を向上
次に、各記事で「AIライティングで何を解決したいか」を文章にしていきましょう
単に「記事を書いてもらう」ではなく、「読者の具体的な悩みを解決し、次のアクションを促す記事を書いてもらう」という目的を設定することで、AIの出力品質が劇的に上がります。
例:「記事作成時間を短縮したい」「SEO対策を自動化したい」「セールスライティング要素を組み込みたい」など
記事制作手順の洗い出し

手順の洗い出しは記事制作においての肝です。
自分が記事を作るときの手順を書き出します。
やりたいけど、自分は上手くできないことなども手順に入れてみるのもアリ!
次に、記事の出力までの各工程を体系化し、AIに段階的に指示できるよう整理していきましょう。
テーマ選定からペルソナ設定、構成決定、トーン調整まで、一連の流れをステップ化することで、毎回同じ品質の記事を安定生成できます。
例:「ターゲット読者の悩み特定→解決策の構造化→AIDMA型構成への落とし込み→CTA設計→最終調整」という流れを、AIが自動実行できるよう言語化
出力条件設定で修正工数を最小化
最後に、AIの出力形式を指定しましょう。
これで、修正作業を最小限に抑えられます。ワードプレスなら一発コピペでブロック化で記事ほぼ完成です!
まじで超便利です。
【指定する出力形式例】
HTMLタグの使用ルール、ショートコードの活用方法、文字数制限、禁止語句など、あなたのブログ運営に必要な条件を事前に設定しましょう
例:「h2、h3見出しにはid属性を付与」「CTAは指定のショートコードを使用」「1章あたり600-800字」「専門用語には必ず説明を併記」などを指定します。

使っているテーマによってショートコードやHTMLの表記崩れがあるので、出力テストしながら調整してみましょう。最初は完成度6割程度で使いながら調整です。
読まれるための修正ポイント

記事の修正で外してはいけないポイントだけ紹介!
CoTで記事を作った後、読まれる記事にするための「ひと手間」を紹介します。この作業が、競合との差別化や検索上位表示の鍵となります。
ここでいう、読まれるとはSEO上位になったり、他の記事を読者に読んでもらうことです。
EEAT要素の追加で信頼性をアップ
GoogleはEEAT(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)を重視しています。難しそうに聞こえますが、要は「この記事、信頼できそう?」という基準です。
2022 年12月のガイドライン改訂でEEATが重視されるようになりました。AIの導入によって、その判定は以前よりもシビアになっています。
いきなりではなく実は2014年から少しずつ導入されており、2022年で大々的に知られるようになりました。

読む人にとって、本当に役立つ記事にしてね!ってこと
Experience(経験)の追加:
「実際に3ヶ月間このシステムを使って...」といった実体験を具体的に記載します。数値や期間を明記することで、読者は「この人、本当にやってるんだ」と感じ、信頼度が格段に向上します。
Expertise(専門性)の証明:
関連する資格や実績、過去の成功事例を簡潔に紹介します。「AI活用歴3年」「記事作成支援実績100件以上」など、具体的な数字で専門性をアピールしましょう。
Authoritativeness(権威性)/ Trustworthiness(信頼性)の構築:
他の専門サイトからの引用や、公式データの参照を適切に行います。また、連絡先やプロフィールページへのリンクを設置することで、「誰が書いているか分かる」状態を作っていきましょう。
関連記事リンクで回遊性を高める

読者の気持ちになっておすすめ記事を提案しよう!
読者が「もっと知りたい」と思った時に、すぐに関連情報にアクセスできる導線を作ることが重要です。
これは読者にとっても、SEO的にもメリットがあります。
文脈に沿った自然な内部リンク:
「詳しいSEO設計についてはこちらの記事で解説しています」といった具合に、読者の興味が湧いたタイミングで関連記事を紹介します。
記事末尾の関連記事一覧:
記事を読み終えた読者に「次に読むべき記事」をお知らせします。「初心者向け」「応用編」「事例集」など、読者のレベルに応じて分類したり、手順ごとにすると効果的です。
読者の疑問を先回りする会話風コメント

課題→解決のサイクルを回すとさくさく読み進めてもらえるよ。
記事を読みながら読者が感じるであろう疑問や不安を、会話風のコメントで表現し、その場で解決というセットにすることで、飽きずに最後まで読んでもらいやすいです。
疑問の顕在化例:
「でも、〇〇って難しそう...」
→ 安心してください!テンプレートがあるので、穴埋め式で簡単に作成できます。
「本当に10分で〇〇できるの?」
→ 最初は20-30分かかるかもしれませんが、慣れれば確実に10分以内になります。私も最初は半信半疑でした。
共感ポイントの挿入:
「分かります、私も最初は『また〇〇の宣伝か...』と思っていました」といった共感コメントを入れることで、読者との距離が縮まりやすいです。
競合記事とのGAPリサーチで差別化

SEO上位&読者に読まれる記事にする大事な作業です
同じテーマで書かれた他の記事と比較し、「この記事だけの価値」を明確にすることで、読者の満足度と検索順位の両方を向上させられます。
チェックポイントは下記です!
情報の網羅性チェック:
競合記事で触れられている内容を確認し、「あの記事にはない情報」を追加します。特に実際の作業時間や具体的な数値データは、他記事との大きな差別化ポイントになります。
5w1Hの洗い出しや自分が行なっている作業で他記事では触れていなかった、他のブログで調べたことなどがないかチェックすると見つかりやすいです。
独自の切り口の追加:
「他の記事では『〇〇ツールで簡単』としか書いていないけど、この記事では『現実的な作業手順』を明記」といった具合に、より現実的でリアルに使える情報を読者に伝えよう。
読者の次のステップまで提示:
多くの記事は「方法を教えて終わり」ですが、「実際に始めるための具体的なステップ」や「つまづいた時の対処法」まで書くことで、もっと役立つ記事になります。
修正作業の効率化テクニック

修正ポイントチェック表を作ってみました!
これらの修正ポイントを毎回ゼロから考えるのは大変なので、チェックリスト化しておきましょう。
私が使っているもので汎用性ありそうなものを抜粋しました!
このチェックリストを使うことで、修正作業も体系化でき、品質の安定した記事を効率的に量産できるようになります。
無料配布:初期プロンプト制作シート

そもそも初期設定部分がすごく大変じゃない?
初期設定を言語化するだけで、やりたいことも明確になっていって便利だけど、自分が考えた項目が足りてるか不安!

ブログ始めたい人が大きな挫折ポイントかつ時間かかるのが初期設定。でもこれをしっかりやっておくと出力の質、変わるのでしっかり時間かけましょう。
CoTの記事制作ルーティン

CoTを使った記事制作todoを決めていこう!自分の苦手なところを洗い出して、CoT以外にもAI活用できる場面を広げていくチャンスが見つかる作業です。
週10時間で10記事投稿の具体的スケジュール
私のある週の制作スケジュールを紹介します。
記事によって変動はありますが、CoT使ってこんな感じで記事を作っています。もちろんこの記事も。
月曜日2時間:
• SEOキーワード選定:30分(10記事分まとめて)
- CoTプロンプト実行:100分(10記事×10分)
水曜日4時間:
• 修正&装飾&図作成:240分(8記事×30分平均)
金曜日4時間:
• 修正&装飾&図作成:120分(残り2記事×60分)
- サムネ制作:30分(10記事×3分)
- 投稿作業&アクセス解析:90分
それぞれの作業の時間配分

それぞれの作業のポイントを紹介します
SEOキーワード選定:30分(10記事分)
まとめて行っていくつかの記事案を作ります。
💡 1つのキーワードから複数記事に展開する例 💡
「アフィリエイト」と「Claude Code」の2つのキーワードの場合
「アフィリエイト」:
・アフィリエイト初心者が稼ぐコツ
・高単価案件の見つけ方
・月10万円達成の具体的手順
「Claude code」:
・Claude code導入から活用まで
・作業効率10倍の実践テクニック
・初心者でもできる自動化設定
※ここまで絞ったら、CoTでタイトルも生成しなおします。
ブログは回遊されることも大事で、複数の記事を段階に分けたりジャンルを分けて制作します。
ラッコキーワードやGoogle Trendsなどのツールを使って、月間検索数とSEO難易度を一括チェックすることで、個別に調査するよりも大幅な時短が可能です。今後
CoTで記事生成:1記事10分×10記事=100分
プロンプトテンプレート(CoT)が完成していれば、ほぼ自動生成できます。
テーマ入力から完成記事まで10分以内で完了するため、従来の手動作成と比べて圧倒的に効率UPできました。徒歩と新幹線ぐらい違います。
修正&装飾&図作成:1記事20分〜40分(平均30分)

まだAIにも限界はあるけど、逆に他のブログや記事と差別もできるところ!
CoT出力の品質により作業時間が変動するんですが8割完成状態なら20分程度、調整が多い場合は40分程度になります。
図表作成やレイアウト調整など、AIでできない部分に集中することで、記事の完成度を高められます。
でも図表作成もAIで時短できます。
サムネ制作:1記事3分×10記事=30分

Canva内にテンプレ作っとけば爆速だあ
Canvaやデザインツールを活用し、統一感のあるサムネをまとめて作成します。
事前にブランドカラーやフォントを統一したテンプレートを準備しておくことで、短時間での量産できます。
このブログのサムネもCanvaで作ってます。サイトと色味を合わせると考える時間少なくて済みます。
あとでいくらでも変えられるので、最初はあまり悩まず仮だと思って作ると挫折回避!
作業ルーティンを決める時のポイント
このサイクルを継続することで、週10記事(月40記事)のペースが維持できます。
記事内容によってかかる時間は変動するので、目安です。
40記事作るもよし、記事制作は10~20記事程度にして、残りの週はより精度を上げたりサイトレイアウトに使うもよしです。

重要なのは、テーマ決めから投稿まで全てを体系化し、迷いなく作業を進められる仕組みを作ることです!
修正や図表作成、サムネ制作など、AIでは代替できない部分に自分の脳と時間を割り当てることで、無理なく続けられる仕組みを作ることができます。
AIを使うと、マーケティングやライティングを1から学んで、練習して・・・という学習コストを大幅に減らせます。
もう一つ重要なことは、作業のバッチ処理化です。バッチ処理とは同じ種類の作業をまとめて行うことで、これで作業効率が向上し、集中力も維持しやすくなります。

人それぞれ苦手ポイントは違うので、自分に合った作業ルーティンにするとストレスフリーで作業を時短できるよ!
資産化システムのためのプロンプト修正方針

読まれる記事を量産し続けるにはプロンプトメンテナンスをしよう
CoT記事量産システムは「一度作ったら終わり」ではなく、Google アップデートやサイト変化に合わせてメンテナンスして、時流にあった記事を量産していきましょう。
もちろん、たまにで十分です。
Googleアップデートに対応する

Googleアップデートは年に数回あるよ
Googleは年に数回、検索アルゴリズムの大きなアップデートを行います。これに対応できないと、今まで上位表示されていた記事が圏外に飛んでしまう可能性があります。
2023年の大幅なアップデートにより大手企業サイトも流入80%減になったところもありました。
【Googleアップデートがあったらやること】
アップデート情報の収集:
Google公式ブログやSEO専門サイトから最新情報を定期的にチェック。「今度のアップデートはEEATを重視」「モバイルファーストがより重要に」といった傾向を早めに把握することが重要です。x(旧Twitter)でも流れてきます。
プロンプトへの反映:
アップデート内容に応じて、CoTプロンプトに新しい指示を追加します。例えば、「記事内に必ず実体験を3つ以上含める」「専門用語には必ず出典を明記する」といった具合に、最新の評価基準をプロンプトに組み込みます。
過去記事の一括修正:
新しいプロンプトで過去記事のリライトを行い、サイト全体の品質を底上げします。この作業も、適切なプロンプト設計により大幅に効率化できます。リライトプロンプトを準備しておくと便利。
サイトコンセプトの変化を反映する

ブログの成長や読者ニーズに対応できるような記事を生み出せるCoTにリニューアルしよう
記事を書き続けていると、「最初に想定していた読者層と実際の読者が違う」「新しいサービスを始めたのでコンセプトを広げたい」といったことがあります。
出力でもう少しこうだったらなーという思いが出てきたらプロンプトを修正することで記事1つ1つの修正が減るので、半年に一度、1年に一度は対応しておきましょう
【チェック事項の例】
読者データの定期分析:
Googleアナリティクスやサーチコンソールのデータを月に1回チェックし、「どんな記事がよく読まれているか」「どんなキーワードで流入しているか」を把握します。これにより、読者の本当のニーズが見えてきます。ここから逆にペルソナを作成していき、プロンプトに反映します。
コンセプトの段階的修正:
いきなり大幅変更するのではなく、「AIツール紹介」から「AI活用したビジネス構築」へといった具合に、段階的にコンセプトを拡張していきます。この変化に合わせて、プロンプトのペルソナ設定や訴求ポイントも調整します。
めんどくさいけど、これをやると記事のネタに困ることもないんです。

CTA導線の最適化をする
CTA(Call To Action)とは:
読者に具体的な行動を促すための誘導文のこと。
「今すぐ登録」「詳細を見る」「無料ダウンロード」などが代表例で、記事を読んだ読者を次のステップに導く重要な要素。
記事が蓄積されると、読者の行動パターンが見えてきます。
この データを活用してCTA導線を最適化することで、収益性を大幅に向上させられます。
CTA効果測定:
「どの記事のCTAがクリックされやすいか」「どんな文言が反応が良いか」を定期的に分析します。
💡おすすめツール:Google Tag Manager、ヒートマップツール
プロンプトへのCTA最適化組み込み:
効果の高いCTA文言やタイミングを特定したら、それをCoTプロンプトに組み込みます。「記事の○○の部分で△△の文言でCTAを挿入」といった具体的な指示により、高い成約率を維持・向上できます。
新しいAI機能やツールに対応する

全部はチェックしきれない...
自分の苦手作業やサイトと相性のいいツールや分野のみで十分

AI技術は日進月歩で進化しており、新しい機能や優秀なツールが次々と登場します。
全部はチェックしなくていいので、あらかじめ自分の苦手作業やサイトの特徴に合わせて相性の良さそうな分野だけチェックするようにしましょう。
自分に合った分野だけを選んでチェックする方法:
記事作成が苦手 → 文章生成系ツール(ChatGPT、Claude等)の新機能をチェック
画像作成が面倒 → 画像生成系ツール(Midjourney、DALL-E等)をチェック
データ分析が苦手 → 分析系ツール(Excel連携、グラフ作成等)をチェック
動画編集に時間がかかる → 動画生成・編集系ツールをチェック
SEO対策がよくわからない → SEO分析・最適化ツールをチェック
AIのリサーチ機能を使って楽にチェックする方法:
ChatGPTに「202⚪︎年⚪︎月の最新AI文章作成ツールをネットで調べて教えて」と指示する。
その際に下記も伝える。
・ブログコンセプト
・現在の読者ペルソナ
・ブログ運営で困ってること
【ツール集め質問例】
「私のブログは○○系です。相性の良いAIツールはありますか?」
「記事作成を効率化できる新しいツールを3つ教えて」
「先月リリースされた便利なAIツールまとめて」
「無料or月額10ドル以内で使える○○系AIツールの最新情報をネットで調べてリストして」

プロンプトの最新情報は特に重要!
CoTもそうですが、プロンプトによって出力の質がすごく変わるので、プロンプト技術が開発されたら、既存システムに組み込めるかテストします。技術の進歩により、さらなる品質向上や時短になります。
これまでに出力を劇的に変化させたプロンプト技術
「Few-shot learning」や「Role-based prompting」、「Chain of Thought」など。
競合サイト定期チェックする
競合サイトを定期的にチェックし、自サイトの差別化ポイントを維持・強化することも大事です。
これもAI使って効率化しましょう。
手動チェック方法(少し面倒くさい)
競合記事の品質チェック: 同じキーワードで上位表示されている競合記事を月1回チェックし、「自分の記事にない情報はないか」「より詳しい解説はないか」を確認します。
簡単チェックリスト:
◻︎ 競合記事の文字数は自分より多い?少ない?
◻︎ 図や表、画像の使い方で参考になる部分は?
◻︎ 見出し構成で「なるほど!」と思う工夫は?
◻︎ 自分の記事では触れていない情報は?
◻︎ CTAの配置や文言で上手だなと思う部分は?
競合分析の結果を基に、「この部分では絶対に負けない」という強みを特定し、プロンプトにその要素を強化する指示を追加します。
AIコーディングで競合サイト分析する(作ってしまえば楽)

キーワード選定とか、記事チェックするとか大変そう・・・!
AIコーディングすれば、もっと簡単にできるよ!

キーワード選定とか、記事チェックするのは地味に時間かかります。
AIコーディングで自分で簡単に作ってしまうこともできます。
Pythonの基礎知識があれば、ChatGPTやClaudeに「競合サイト監視システムのコード書いて」と依頼するだけで、コードが手に入ります。
実際に使えるようにすることをデプロイと言いますが、デプロイもAIの指示に従って行います。
Railwayなどのクラウドサービスを使えば、月500円程度で自動運用が可能です。
500円のクラウド契約で複数の自作コードを走らせることができます。
構築するシステム例
・競合記事のタイトル・見出し・文字数の自動収集
・検索順位の変動を毎日自動チェック
・競合が新記事を投稿したらSlack/Discordに通知
・月次レポートを自動生成してメール送信

バイブコーディングというラフにやって欲しいことを投げるだけで、コーディングが簡単にできるようになりました。
以前よりも本当に簡単にコーディングできるようになっています。
ただし、気をつけることもあるので下記の記事も参考にしてみてください。
-
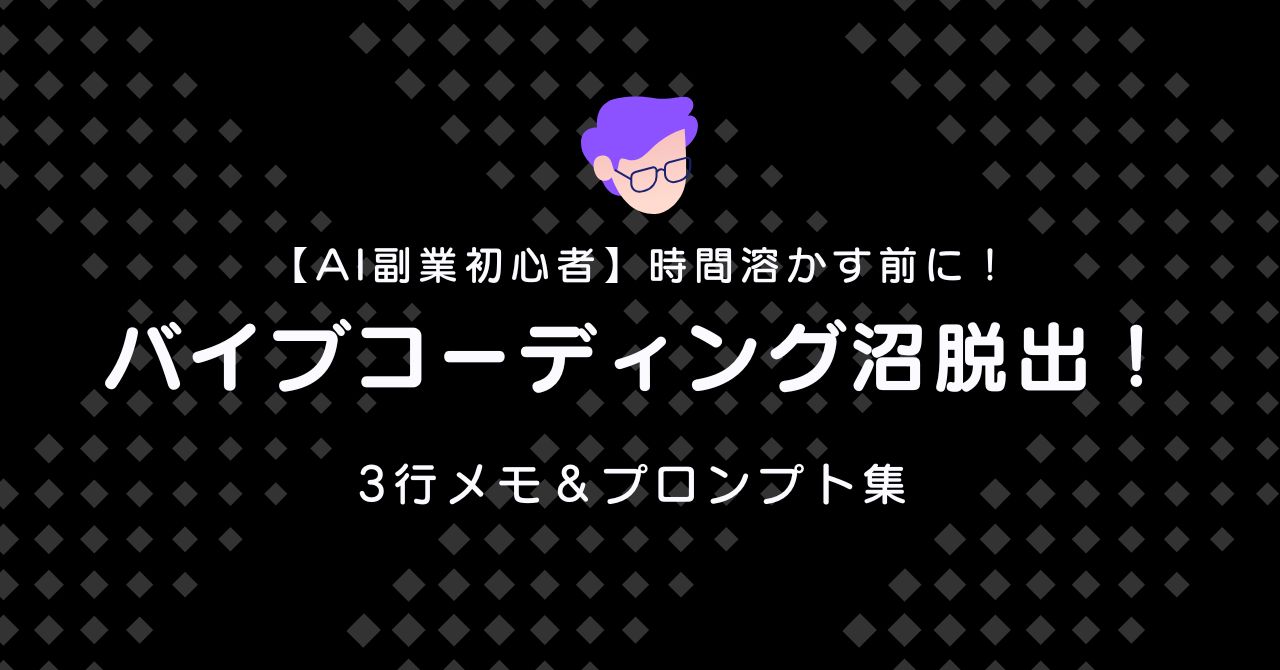
-
【AI副業初心者】時短術!脱バイブコーディングプロンプト例
AI時短術 バイブコーディング沼脱出プロンプト ChatGPT や Claudeを使ってプログラミングに挑戦した人が一度はぶつかるエラー修正。 本記事では バイブコーディング(雰囲気コーディング)の落 ...
続きを見る
必要な技術要件も記載しておきます。
まだ基礎知識がないという人はYoutubeやUdemy、格安の基礎講座を利用して数日〜2週間程度で身につけられます。
競合サイト定期チェックシステムに必要な技術要件:
◻︎ Python基礎知識(if文、for文が分かる程度)
◻︎ クラウドサービスの基本操作(Railway、Heroku等)
◻︎ HTML/CSSの軽い理解(要素を特定できる程度)
※個人ブログの競合分析程度のスクレイピングは、常識的な頻度であれば法的に問題ないです。DOS攻撃にならないように間隔に気をつけましょう
メンテナンススケジュールの例

カレンダーアプリに入れておくと忘れない!
メンテスケジュールの例をまとめておきます。
毎月:アクセス解析・CTA効果測定・競合サイトチェック
四半期:プロンプト大幅修正・過去記事リライト計画
半年:サイトコンセプト見直し・新AIツール検証
年1回:システムやプロンプト全体の見直し
定期的なメンテナンスは、たまにで大丈夫ですが、継続的に収益を生み出すブログに育てるために確実に役立ちます。
ブロガーはもっと人気の仕事になる

AI使いこなすブロガーは有能です!
CoTで記事量産システムを構築できるようになると、あなたはただの「記事を書く人」から「エディター・キュレーター」になります。
これからの時代、そんなブロガーはますます価値の高い存在になっていきます。
情報過多時代のキュレーターとしての価値
毎日とんでもない量の情報がインターネットに投稿されています。ニュース、SNS、YouTube、ブログ...多くの人は「どの情報が正しいの?」「何を信じればいいの?」と迷ってしまいます。
そこで活躍するのが、CoTをはじめとしたAIを使いこなせるブロガーです。
ブロガーは元々情報感度が高いので、膨大な情報の中から「本当に大切なもの」を見つけ出し、読者に分かりやすく伝えることができます。これって、すごく価値のあるスキルなんです。
企業も「情報を整理して、お客さんに分かりやすく説明できる人」を探しています。
AIが普及するようになってさまざまな案件が増えています。
AIで情報を分析・再構成する能力は、まさに企業が欲しがるスキルなんです。
資格だけでなく、実際に使っている実績をブログで体現したり発信することをやっているというのが大事。
単なる情報収集ではなく、「読者に合わせた情報の翻訳」ができる人材は、これからもっと貴重になります。
AIが使える新しいブロガー像

まだAI使いこなしてるブロガーは少数だ!
AIDMA・PAS構造をはじめ従来のマーケティング手法や情報分析手法をAI活用しながらを自然に使いこなせるようになると、ブロガーの可能性はブログだけでなく、色々広がります。
【AI活用能力のあるブロガーのピボット例】
マーケティング担当として:
「どうやったらお客さんに商品を買ってもらえるか」を考えるのが上手になります。セールスライティングができるブロガーは、企業からとても重宝されます。
インフルエンサーやコンサルタントとして:
読者の心理を深く理解できるようになるので、SNSでの影響力も自然と高まります。「この人の言葉は心に響く」と感じてもらえるようになり、個人ブランドが強化されます。
教育・研修分野での活躍:
AI活用で身につけた「体系化された思考プロセス」は、人に教える時にもとても役立ちます。「考え方を教える先生」としての需要も生まれます。
AIを使いこなせるブロガーは、まだまだ少数派です。
だからこそ、今行動を起こせば「この分野の先駆者」にほぼ間違いなくなれます。
重要なのは、汎用的なAI活用ではなく、自分のやりたいことやコンテンツに特化した仕組み化です。
商品・ターゲット・トーンを明確化し、セールスライティングの型を組み込んだCoTプロンプトにより、修正工数を80%削減しながら売れる記事を量産するだけじゃなく、他にもいろんなことができます。
AI活用は単なる作業効率化ではなく、あなた自身の「価値」を大きく高める投資になるので、ぜひAIを活用してスキルアップや時短、自分のコンテンツを作っていきましょう!