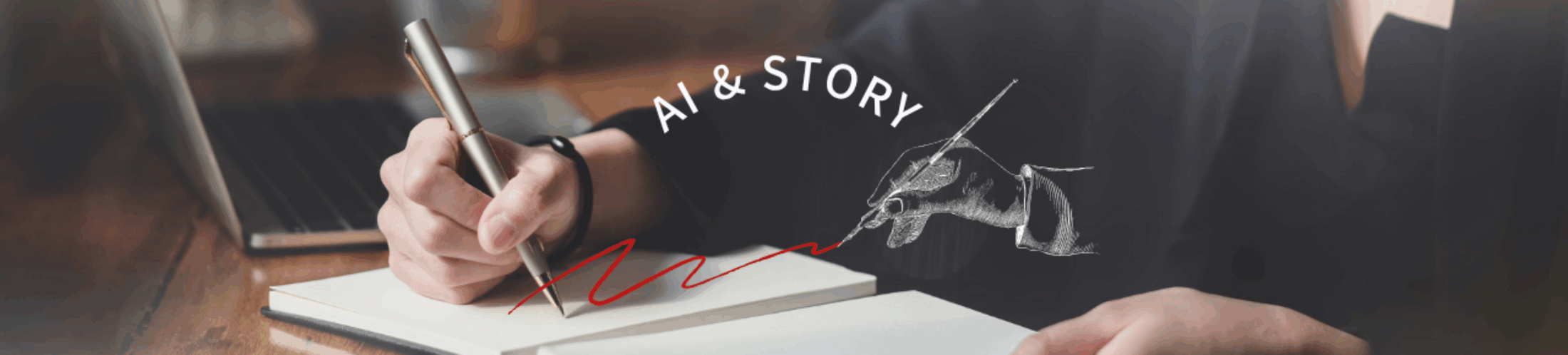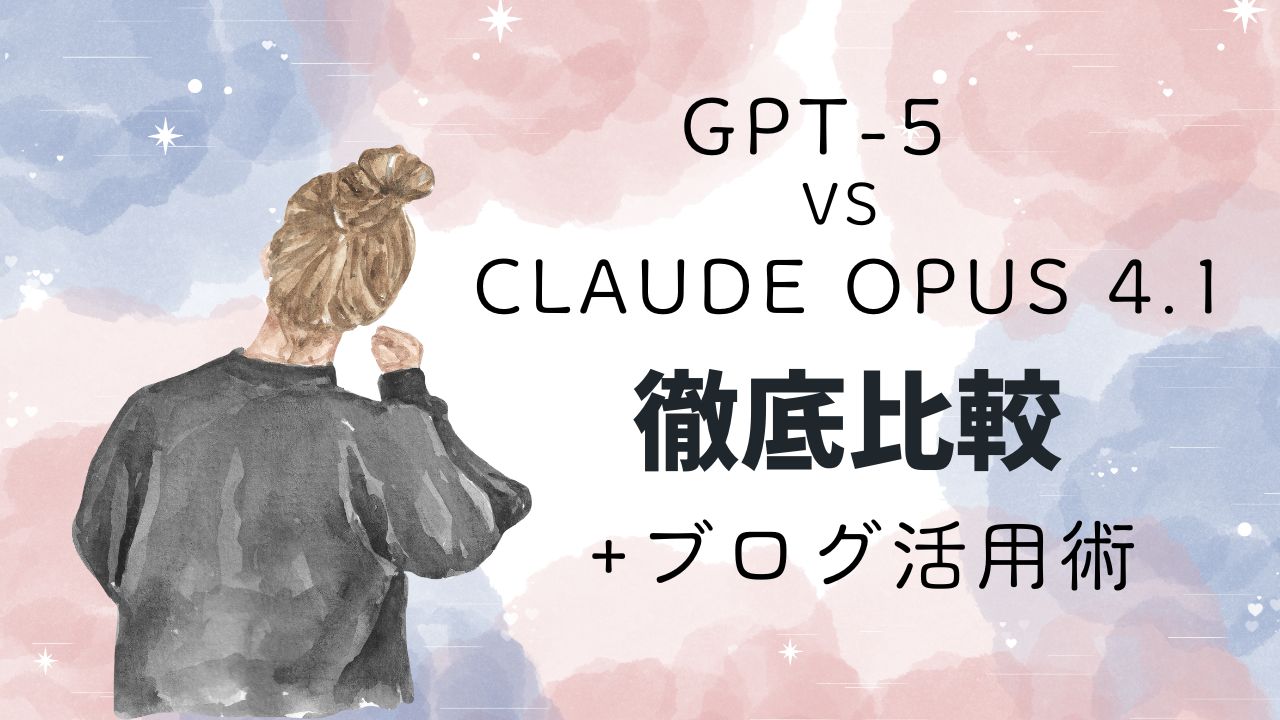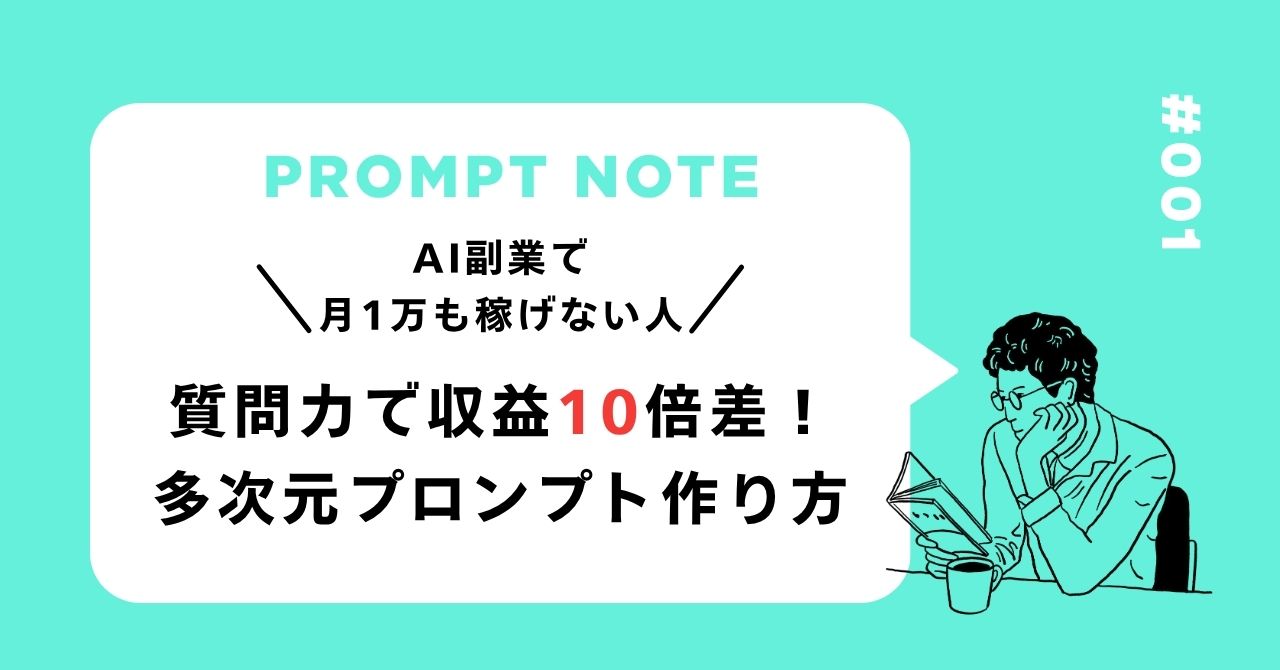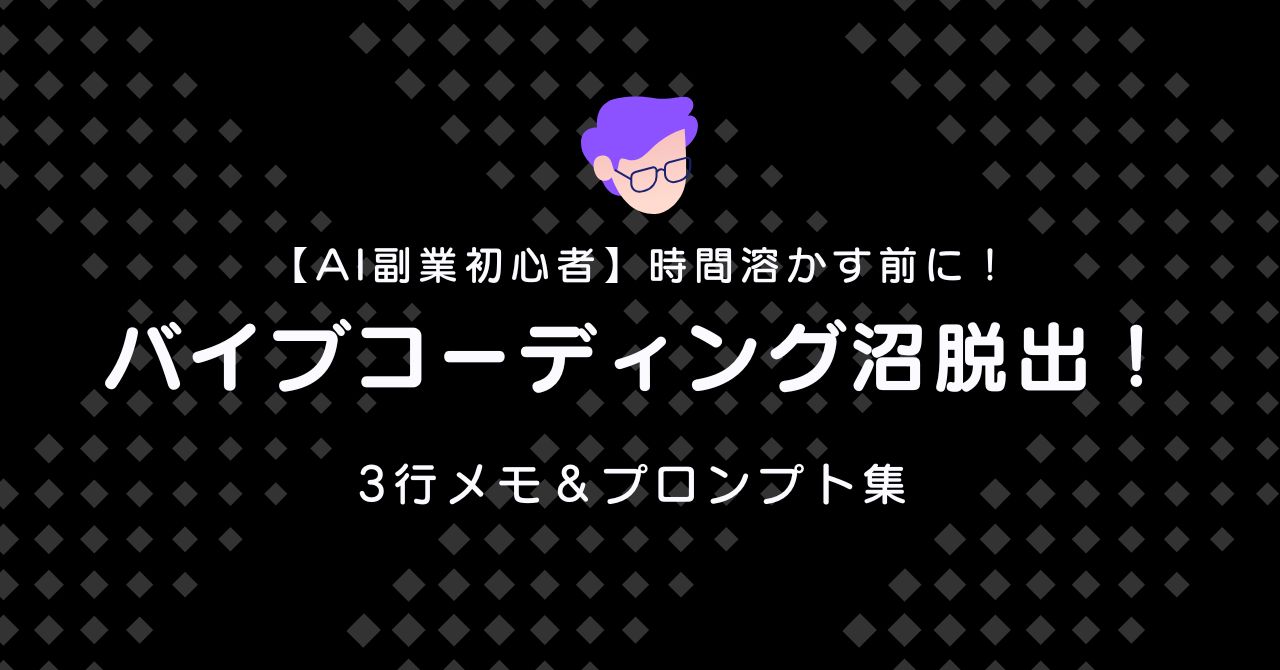GPT5の概要とClaudeとの比較、ブロガー向けプロンプトも考えてみました!
AIモデルが次々と進化を遂げる中、2025年8月7日ついにOpenAIのGPT-5がリリースされました。
8月5日はAnthropicのClaude Opus 4.1も登場。
どちらも“現時点で最強クラス”と呼ばれる性能を持ち、文章生成や推論タスクで高い評価を得ています。
しかし、いざ使ってみようとすると
「結局どっちが自分に合っているの?」
「どう使い分ければ効率的?」
と迷う人も多いはず。
GPT-5とClaude Opus 4.1の性能・特徴の違いをわかりやすく比較し、
さらにブロガーが記事制作やSEO対策に活かせるプロンプト例もご紹介します。
AIをまだ触ったことがない方も、
すでに使っているけどもっと活用したい方も、
この記事を読めば自分に合ったモデル選びと効果的な使い方がわかります。
ぜひ最後までチェックして、今日からAIをあなたのブログ運営の強力なパートナーにしてみてください。
GPT-5の基本概要と進化ポイント

今までと何が違うんだろう? 無料ユーザーも使える?
GPT-5は無料プランでも利用可能です。
最大の特徴は、用途に応じて高速応答モードと深い推論モードを自動で切り替えるリアルタイム・ルーター機能と、o3を上回る高度な推論力です。
もっと簡単にすると?

従来は「速いけど浅い」か「遅いけど深い」をユーザーが選ぶ必要がありました。
GPT-5は内容に合わせて自動で切り替えるため、
軽い質問はサクッと、難問はじっくり(o3以上の深さ)考えて答えられるようになりました。

速さと精度の両取りができるようになったよ!
リリース日と提供状況(無料・有料プランの違い)
リリース日:2025年8月7日
ChatGPTの全ユーザーが利用可能です。
無料プランでは1日の使用回数に制限がありますが、
有料プラン(Plus)ではほぼ無制限に利用できます。
高精度な「Thinkingモード」も無料でも試せますが、長時間利用する場合はPlusが推奨です。
GPT-4oやo3との大きな違い
推論力の向上:o3と比較して複雑なタスクや計算で精度が向上
自動モード切替:軽い質問は高速モード、難問はThinkingモードへ自動遷移
最大256,000トークンの長文対応:長い文章や複数資料の同時解析が可能
Thinkingモードとは何か

Thinkingモードってなんなの?
Thinkingモードは、通常モードよりも長く考える時間を取り、段階的に推論して回答するモード。
これにより、事実の精度や論理的整合性が大幅に向上します。
公式ベンチマークでは、難易度の高い質問で誤情報率が大きく減少しており、
特に複雑な分析やコーディング、戦略立案などに効果を発揮します。
スポンサーリンク
o3を超える推論力と精度改善の裏付け
GPT-5は、前世代のo3を上回る推論力を備えています。
特に「Thinkingモード」では、回答までに十分な思考時間を確保し、
事実の確認や論理構成を段階的に行うことで精度を高めて、ユーザー満足度の高い内容を出せるようになっています、
その結果、複雑な課題でも一貫性のある、信頼できる答えを返せるようになりました。
ハルシネーション率の大幅減少

AIでありがちなハルシネーションがどうなったか知りたい。
出力量の増加と質の向上でハルシネーションに気付きにくくなってて困ってた...。
OpenAIのテストによれば、
GPT-5 Thinkingモードの誤情報率(ハルシネーション率)は、o3の約15.8%から1.6%へと大幅に減少しました。
これは、事実に基づいた回答が必要な分析や戦略立案などで、より安心して使えることを意味します。

引き続き、ユーザーに求められるのは、出力をチェックする目であることは変わらないですね。
複雑なタスクでの精度向上事例

高度な推論力は、実際の作業効率や成果にもつながるって言われるけど、
具体的にどんなふうに進化したの?
3つの分野でこのように推論が向上しました。
数理・論理パズル:中間計算や仮説検証を丁寧に行い、正答率が向上
コーディング:仕様の理解からデバッグ提案まで一貫して正確
長文分析:複数資料の要約や比較で情報抜けや矛盾が減少
つまり、作業のやり直しや追加調査の手間を減らし、より速く、より確実に目的達成できる可能性が高まります。
修正頻度や、根本的な方針転換の指示をする頻度が減ります。
Thinkingモードの強みと限界

プロンプトでコントロールしなくても、強制的に深い推論をしてもらえるのがThinkingモードぉ!
強みは、高精度で一貫性のある推論が可能なことです。
一方で、処理に時間がかかるため、短い応答がほしい場面や軽い作業には不向きな場合があります。
そのため、
日常的な雑談や簡単な検索的質問は通常モード、
重要な判断や分析はThinkingモード、と使い分けるのがおすすめです。
Claude Opus 4.1との比較と使い分け

Claude Opus4.1との使い分けを知りたい!
Anthropicからも対抗馬として2025年8月5日にリリースされたClaude Opus 4.1は、
GPT-5と同様に高い推論力と応用性を兼ね備えたモデルです。
ここで両者を比較し、それぞれどんな場面で活用すれば効果的かを見ていきましょう。
性能と推論スタイルの違い

まずは両者の特徴から掘り下げていくよ!
Claude Opus 4.1:ハイブリッド思考(即時応答+段階的推論)に対応。特にコーディング/SWE-benchのスコアは74.5%で、GPT-o3の69.1%を上回り、精度に定評あり (出典:venturebeat.com)
GPT-5:用途に応じて高速モードとThinkingモードを自動切り替え。
最大256,000トークンの長文に対応し、深い分析や対話にも強みあり。
256,000トークンとは、前世代のGPT-4o(約128,000トークン)の2倍、
一般的な小説約500ページ分の文章を一度に処理できる計算。
長編記事や複数資料をまとめて分析するような作業でも、途中で文脈が途切れにくくなりました。
文章・創作能力の特徴

アウトプットに合わせて使い分けたいですね
Claude Opus 4.1は、キャラクター表現や創作の自然さに秀でており、深みがあり自然な語り口や情景描写のある文章やストーリー制作に適しています。
一方GPT-5はプロンプトによる柔軟な調整が得意で、
ブロガーが意図通りの文体や論理展開を引き出しやすい傾向です。

個人的にはセールスライティングを用いたブログ記事はGPT-5に軍配をあげたい!
ストーリー系のショート動画の台本はClaude Opus4.1でした。
タスク別おすすめモデル選び

どんなタスクにどのモデル使えばいいかな?
構造的な文章や創作重視:Claude Opus 4.1がやや優勢
精緻な推論/情報分析:GPT-5のThinkingモードを使うことでo3を超える精度を発揮
長文・複数資料の同時処理:GPT-5の大コンテキスト対応が力を発揮
コーディングやデバッグ支援:Claude Opus 4.1のSWE-bench高スコアと安定性は魅力的
多くの現場でClaudeの文脈保持力とエージェント的な動作が評価されており、
「長客文を扱う分析・計画系の作業」、「自然なリライト制作」などにおいて非常に力を発揮すると報告されています。
(参考資料:tomsguide.com)
スポンサーリンク
GPT-5で使える新しいパラメーター

GPT5の新機能を教えて欲しい!
GPT-5のAPIには、出力の「長さ」と「思考の深さ」を調整できる新パラメーターが追加されています。
うまく使うと、無駄な長文や“浅い推論”を減らし、
目的に合った回答を安定して得やすくなります。
「verbosity」で出力の詳しさをコントロール

verbosity = 冗長性って意味だよ。長い、詳しすぎるみたいな感じ。
verbosityは回答の詳しさの目安を指示するつまみです。
値は low / medium / high。
lowなら要点だけ、highなら解説や補足まで厚めに出ます。
まずはデフォルト(medium)で使い、読み手や用途に応じて切り替えるのがおすすめです。
「reasoning_effort」で思考の深さを調整

お話聞いて欲しかったり、情報の詳しさ(粒度)が低くてもいい時もあるもんね
reasoning_effortはモデルがどれだけ“考えるか”の強度を決めます。
minimal / low / medium / high(モデルにより提供値は異なる)。
minimalやlowはスピード優先、highは正確性・一貫性を優先した深い推論に向きます。
複雑な分析・設計・コーディングなどはhigh、雑談や要約はminimal〜lowが目安です。
初心者でもすぐ試せる“設定例”と代替プロンプト

知りたいこと、今までうまくいかなかった事柄についてぜひ下記のプロンプト試してみて!
短く要点だけ欲しい:(設定例)verbosity=low/(代替プロンプト)「要点のみ3行で」
丁寧な解説が欲しい:(設定例)verbosity=high/(代替プロンプト)「背景→手順→注意点の順で詳しく」
深い推論が必要:(設定例)reasoning_effort=high/(代替プロンプト)「結論→根拠→反例→前提の順で検証して」+「必要なら思考時間を長めに取って」
スピード重視:(設定例)reasoning_effort=minimal/(代替プロンプト)「結論だけ先に短く」
ポイントは「まずは目的(速さか精度か)を決めてから、
verbosityとreasoning_effortを合わせて調整する」こと。
UI(ブラウザ版やアプリ版のChat GPTのチャット画面)でパラメーターが見当たらない場合でも、
上の“代替プロンプト”でかなり近い挙動に寄せられます。
スポンサーリンク
精度を引き出すプロンプト設計のコツ(GPT-5版)

うまく使いこなすプロンプトのコツ知りたい
「Let’s think step by step」はこれまでのモデルと同じように有効ですが、
GPT-5では深い推論モードの活用・長文前提・自己採点まで踏み込むと、
精度と再現性が上がります。
ここではGPT-5向けに上乗せすべき要素に絞って紹介します(すべてコピペ可)。
GPT-5ならではの“思考指示”を追加する
速さ/深さを明確化し、モデルの内部思考は要約だけ出させるのがコツ。
目的:精度優先。必要なら思考時間を増やしてから回答してください。 出力規範:①結論(先に)②高レベルの根拠要約③反例・限界④次アクション 非公開思考:内部の詳細推論は開示せず、要約のみ提示すること。 優先度:事実整合性>網羅性>簡潔さ(速さは二の次)
なぜ: GPT-5は内容に応じて深く考えられます。最初に「精度優先」「思考時間を増やす可」を宣言すると、浅い即答を避けやすくなります。
2段構成(Draft → Critique)で仕上げ精度を上げる
初稿と自己レビューを分けると、取りこぼしや論理飛躍が減ります。
手順: 1. Draft:結論→根拠→前提→反例の順で初稿を作成 2. Critique:初稿に対し「事実誤り」「飛躍」「不足データ」を指摘し修正 制約:修正箇所は理由付きで明示。不要な言い換えは禁止。
なぜ: GPT-5は自己検証の指示に反応しやすく、2パス化で精度を底上げできます。
先に“採点基準(Rubric)”を与えて自己採点させる
ゴール像を明示すると、回答のブレが減ります。
評価基準: - 正確性:一次情報の整合(3点満点) - 論理構成:前提→手順→帰結の一貫性(3点) - 実用性:具体手順/例の明確さ(2点) - 明瞭性:冗長表現なし/重要語を太字(2点) 回答後に10点満点で自己採点し、減点理由と改善を一行で。
なぜ: GPT-5は明確なルーブリックで出力を“合わせに行く”挙動が強いです。
長文前提の“分解+トークン節約”指示
大きな課題は分割・参照で扱うと安定します。
分解方針: - 課題を3サブタスクに分割し、順に解く - 各サブタスクは200〜300語上限、要点だけ - 参照:資料A(要旨1行)、資料B(要旨1行)を使い、出典名を括弧で示す - 最後に統合要約(150語以内)と残課題を列挙
なぜ: GPT-5の長コンテキストでも、明示的な分割・参照ルールがあると誤読・脱線を防げます。
不確実性・前提を“数値で”表明させる
曖昧さを残すなら、読者が使える形に数値化します。
不確実性の扱い: - 自信度(0〜100%)を最後に表示 - 追加で必要な情報を3点以内で列挙(取得手段も一言) - 代替案:前提Aが違う場合の結論も1行で示す
なぜ: 答えの“使い所”が明確になり、実務で判断しやすくなります。
タスク別:中級者向けテンプレ改訂版
- コーディング
要件:機能/入出力/制約/境界値を列挙→最小実装→失敗テスト→修正提案
品質:計算量O()、副作用、エラーハンドリング、再現手順を必ず記載 - 文章生成(ブログ)
読者像/検索意図/避けたい口調/禁止ワードを冒頭に宣言
構成:導入AIDA→H2/H3設計→本文→要約→CTA
検証:事実/引用/比較表の有無をチェックし不足あれば追記 - 分析・戦略
フレーム:結論→ドライバー→データ根拠→リスク→打ち手(短/中/長期)
反証:逆仮説を1つ検討し、意思決定の分岐条件を数値で示す
ブロガーがGPT-5を活用する方法

ブロガーはどうやってGPT-5を使えば良さそうかな?
GPT-5は文章生成力と推論力の両方が高いため、
ブログ運営において記事制作の時短・質の向上・SEO強化に直結します。
ここでは、ブロガーが日常的に使える具体的な活用シーンとプロンプト例をご紹介します。
記事構成づくりを時短するプロンプト例

これまで使ってるプロンプトでも精度上がっています。つまり修正がかなり減る。
記事構成をゼロから考えるのは時間がかかります。
GPT-5に条件を与えると、読者ニーズに沿った見出し案をすぐに生成できるプロンプトです!
テーマ:[記事テーマ] ターゲット読者:[想定する読者層] 検索意図:[想定する検索キーワードや目的] 条件:H2とH3の見出し構成を提案し、それぞれ簡単な説明も添えてください。
【入力例】
テーマ:[GPT-5の活用方法とすんごい精度出るプロンプト例]
ターゲット読者:[GPT-5がすごいと聞いて、AIで何かを始めたい人、初心者]
検索意図:[GPT-5活用 初心者向け解説]
条件:H2とH3の見出し構成を提案し、それぞれ簡単な説明も添えてください。
このプロンプトを使えば、テーマと読者像を入力するだけで、
骨組みのしっかりした構成案を数分で得られます。
見出し構成案の段階で足りない項目があれば追加して構成案を作ってから本文出力に移ると、文章が迷子になりません。
SEOキーワード調査&見出し生成

既存のSEOツールやキーワード選定ツールのCSVなどを活用するとさらに精度上がります
キーワードリストを作る作業もGPT-5で効率化できます。
Thinkingモードを使えば、関連キーワードや競合との差別化ポイントまで考慮した提案が可能です。
対象キーワード:[メインキーワード] 目的:SEO上位を狙う記事構成の作成 条件: 1. 関連キーワードを10個提案(検索ボリュームや競合度の目安付き) 2. その中から優先度の高いものを使って見出し構成を作成
ハルシネーションを防いだり、日本向けに特化したキーワード選定を行うには、
専用のツールと組みわせる方が、検索上位狙えます。
リライト・要約・アイキャッチ文の自動化
既存記事の質を高めるリライトや、SNS向けの短い紹介文もGPT-5に任せられます。
元テキスト:
[リライトや要約したい本文を貼る]
条件:
- PREP法を用いて、専門用語を極力避けて簡潔に書き換える
- SEOキーワードは維持
- タイトル用とSNS用(100文字以内)の短文も作成
これにより、1記事から複数のアウトプット(本文・要約・SNS告知文)をまとめて生成でき、作業効率が飛躍的に上がります。
ブログ運営は「質」と「更新頻度」の両立が鍵です。
GPT-5を活用すれば、ネタ出しから執筆、リライト、SNS展開までを一気通貫でこなせる体制が作れます。
GPT-5が向いている作業 向いていない作業

向き不向きを知ることがAIを使う側か使われる側かの分かれ道!
GPT-5は万能ですが、すべての作業で常に最適というわけではありません。
得意な場面とそうでない場面を見極めることで、時間とリソースを無駄にせず活用できます。
短時間で済む作業
- ブログ記事のタイトル案やキャッチコピーの生成
- 短い要約やSNS投稿文の作成
- 単純な事実確認や軽いQ&A
こうした場面では高速モードが有効。即レスで複数案を出してもらい、必要に応じて人が取捨選択します。
深い推論が必要な作業
- 複雑なテーマの記事構成づくり
- 競合分析やSEO戦略立案
- 複数資料をまとめたリサーチ記事の執筆
- プログラムの設計やエラー原因の特定
Thinkingモードを使うことで、論理の抜けや事実誤りを減らし、精度の高いアウトプットが得られます。
不得意な作業を見極める
- 最新の速報ニュースの正確性確認: リリース直後の情報や数時間単位で変わる数値は誤差が出やすい
- 感情や文化的ニュアンスが極めて重要な文章: 詩・文学の高度な表現はまだ人間の方が安定
- 法務・医療など資格領域の最終判断: 参考情報には使えるが、専門家のチェックが必須
- 事実確認を伴わない推測: 自信度が低いまま断定するケースがあるため注意
こうした領域では、GPT-5を初稿や叩き台として活用し、最終的な検証や表現調整は人間が行うのが安全です。
他ツールとの組み合わせ例
- NotionやGoogleドキュメント:記事構成やメモを直接保存・整理
- キーワード分析ツール:GPT-5で候補を作り、検索ボリュームを専用ツールで確認
- 画像生成AI(MidjourneyやLeonardo AI):記事のアイキャッチや挿絵を自動生成
- 音声読み上げツール:記事をポッドキャストや動画に再利用
単体での利用にこだわらず、他のツールと組み合わせることで、作業の幅とスピードはさらに広がります。
まとめ&今すぐ試すためのステップ

Chat GPTで早速コーディングやブログ執筆してみよう!
GPT-5とClaude Opus 4.1は、それぞれ異なる強みを持つ最新AIモデルです。
GPT-5は高速モードとThinkingモードの自動切り替え、大容量コンテキスト、精度を引き出すための多彩なプロンプト設計が魅力。
一方で、Claude Opus 4.1は自然な文章生成や安定したコーディング性能に強みがあります。
大切なのは、両者を「どちらが優れているか」で比べるのではなく、
目的や作業内容に合わせて使い分けることです。
特にブログ運営やコンテンツ制作では、この使い分けが成果に直結します。
まずは無料プランで触ってみる
GPT-5もClaude Opus 4.1も無料で試せる環境があります。
まずは短時間の質問や軽い作業で触れて、応答の違いや得意不得意を体感しましょう。
Thinkingモードを体験してみる
精度が求められる作業では、GPT-5のThinkingモードをONにして試してください。複雑な記事構成やリサーチ記事などで、通常モードとの違いが明確にわかります。
プロンプトテンプレを試すリンク/コピー案内
この記事で紹介したプロンプトテンプレートや設定例は、そのままコピーして使えます。
まずは1つ、自分のテーマで試し、出力の質や作業効率がどれだけ変わるかを確認してみてください。