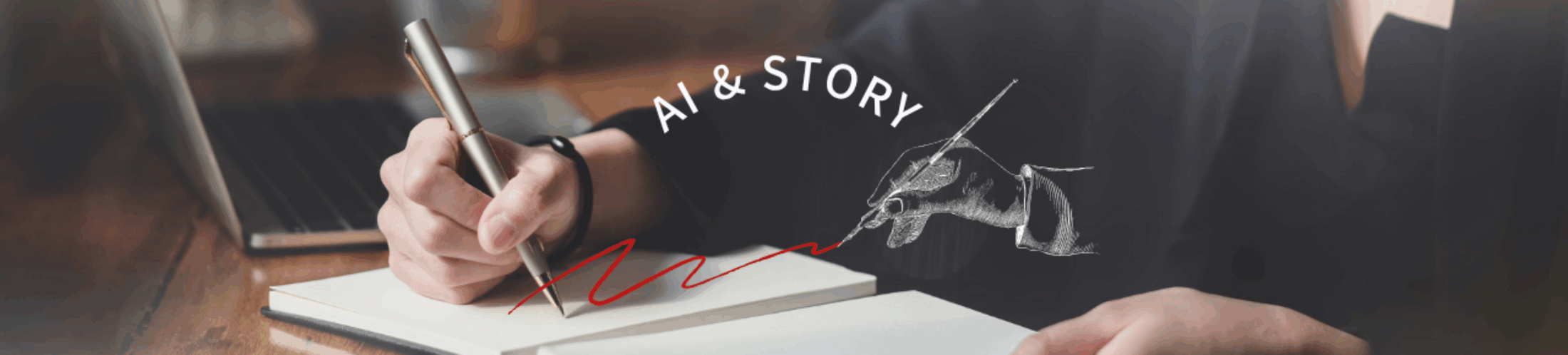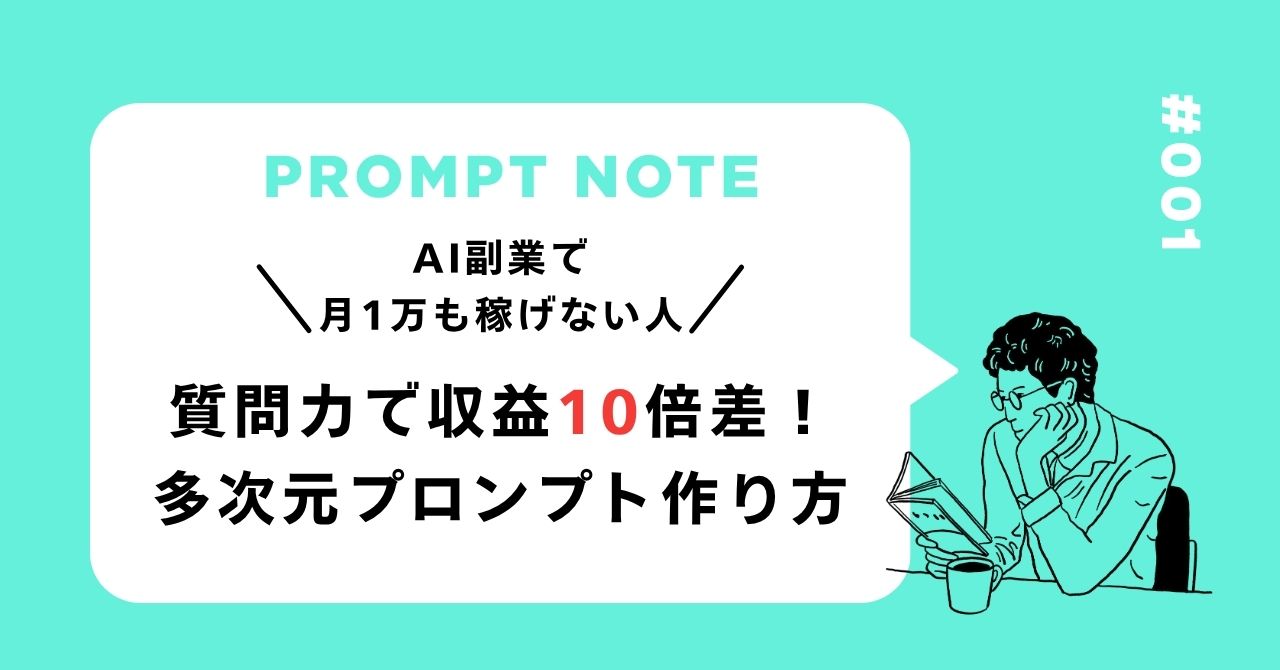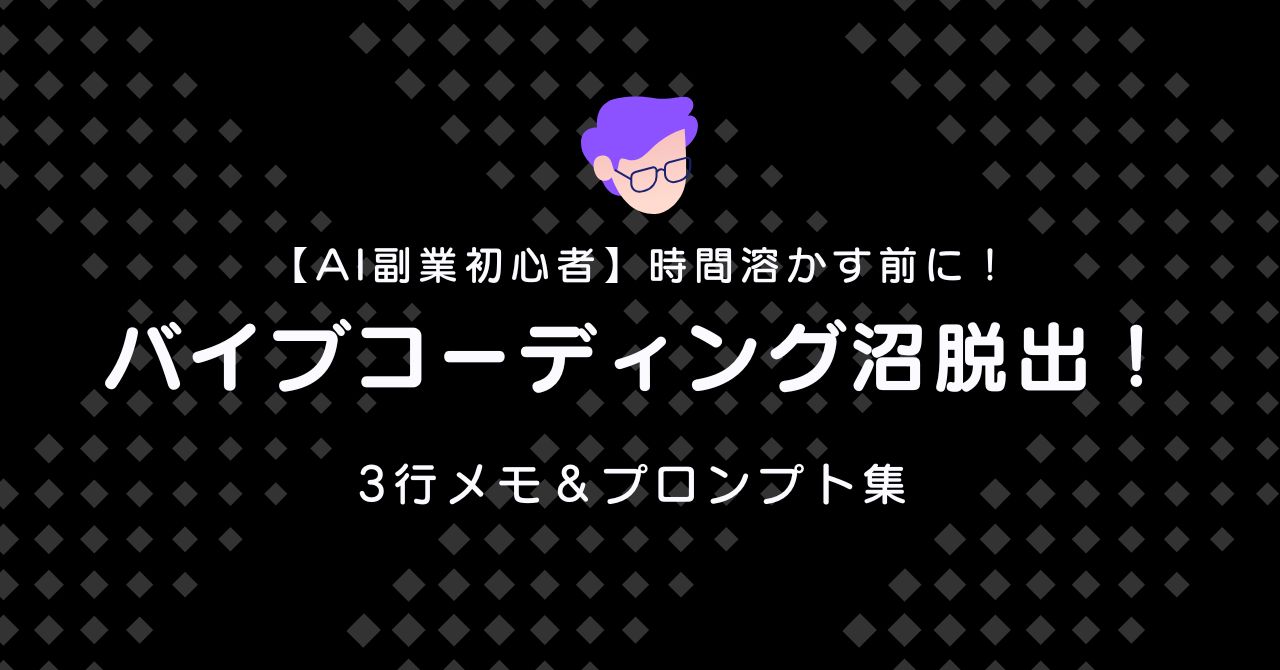TOEICスコアを効率的に伸ばす勉強方法と効率UPツールを紹介します!
TOEICの勉強って、やろうと思っても仕事や学校で時間が取れないこと、多いですよね。
私も同じで、まとまった勉強時間なんてなくて「これじゃスコアは伸びないんじゃないか」と悩んでいました。
実際に思ったように伸びなかったり、勉強自体がすごくストレスに感じることもあって挫折したこともありました。
しかしその後、週10時間×2ヶ月でもスコアを200点近く伸ばすことができました。
カギになったのは、戦略的な学習サイクルと、デジタルツールを使った効率化です。
この記事では、私がTOEIC900に近づけた学習法をまとめます。
同じように「時間はないけど効率的にスコアを上げたい」という人の参考になれば嬉しいです。
こんな人におすすめ
- TOEIC600〜700点台から、短期間で900を目指したい人
- 忙しくて勉強時間が取れない社会人・学生
- 紙よりデジタルで効率的に学習したい人
- mikanやiPadを使っている/使おうと考えている人
- 「具体的に何をやればいいか」を知りたい人
時間がないけどスコアを伸ばせた理由

スコアを伸ばすにはコツがあります!
TOEICを勉強していると、周りから「毎日何時間も勉強してるんでしょ?」とよく聞かれます。
でも実際はそんなに時間を取れていません。
私も平日は30分〜1時間、週末に少しまとめてやるくらいでした。
それでもスコアを伸ばせたのは、次の3つを意識したからです。
短時間でも成果を出す効率学習

通常の勉強自体は1日1時間程度でOKでした
「時間が足りない」と思っても、実は毎日1時間前後でも十分スコアは伸びると実感しました。
大事なのは長時間やることではなく、短い時間でも集中して正しい方法で積み重ねることです。
やみくもに勉強せず「伸びる部分」に絞った

自分のボトルネックを正しく認識することも大事です
全部のパートを完璧にしようとすると、時間がいくらあっても足りません。
そこで私はリスニングで470点以上を確実に取ることを優先しました。
リーディングは全問正解を狙わなくても良いので、「落としていい部分」を決めて安心して勉強できました。
ツールを組み合わせてムダをなくした

紙ノートからデジタルノートにしたことで効率化が進んだ!
mikanで単語や文法を学び、GoodNotesに間違えた問題をまとめてタグ管理。
(mikanとGood Notesの使い方については後述します)
iPadとペンシルで勉強を一元化したことで、
「どこにメモしたっけ?」というムダがなくなり、勉強効率が一気に上がりました。
この3つを意識するだけで、「時間がないから無理」という思い込みが消えます。
私もそうでしたが、正しい方向でやれば短い勉強時間でも成果は出せるんです。
このあと、より具体的に「週10時間×2ヶ月で900点を目指す学習戦略」を紹介していきます。
スポンサーリンク
週10時間×2ヶ月で900点を目指す学習戦略

締めるところ締めて、緩めるところは緩めてこー!
TOEIC900を目指すときに大事なのは、「全てを完璧にしようとしないこと」です。
私が実際にやったのは、点数が伸びやすい部分に集中する戦略でした。
リスニングで470点以上を狙う理由

リスニングは短期間で伸びやすいです!これは再現性が特に高いです。
TOEICはリスニングの方がスコアを上げやすい試験です。
リーディングよりもクセが少なく、正しいトレーニングをすれば短期間でも点数が伸びやすいのです。
私はリスニングで470点以上を確実に取ることを第一目標にしました。
リーディングは全問正解でなくてもOK(配点戦略)

精読と速読の判断や、判断できてもこなすには反復が必要でちょっと時間かかるんです
リーディングは200問ありますが、全問正解を狙う必要はありません。
特にPart7の長文読解は、正直「全部解く」のは時間的にかなり厳しいです。
私は自分が落としても良い問題をあらかじめ決めて、その分を他の問題で確実に得点する方法をとりました。
この「配点戦略」を使うことで、精神的にもラクになり、集中力も続きやすくなりました。
8週間の学習ロードマップ概要
私が組んだ学習スケジュールは、ざっくり次のような流れです。
1〜2週目: mikanで単語・文法を徹底強化(基礎固め)
3〜4週目: リスニング特化。公式問題集で実戦感覚を養う
5〜6週目: リーディングPart5・6を集中的に演習
7週目: リーディングPart7(長文)を攻略。GoodNotesで間違えた問題を整理
8週目: 模試形式で仕上げ。Udemy講座も活用して苦手を補強
このように、2ヶ月を「基礎 → リスニング強化 → リーディング補強 → 仕上げ」と区切ることで、
毎週の勉強がシンプルになり、迷わず進められました。
次は、この戦略を支えたアプリとノートの組み合わせについて紹介します。
使ったアプリとノートの組み合わせがカギ

タイパを爆上げするために必須のツールです
2ヶ月でTOEICスコアを200以上伸ばせた最大の理由は、学習ツールをうまく組み合わせたことでした。
特に「mikan」「GoodNotes」「iPad+ペンシル」の3つは、勉強効率を大きく変えてくれました。
mikanで単語・文法・例文を効率的に習得
TOEIC学習の土台はやはり単語と文法です。
私はmikanをメインに使って、単語・文法・例文をテンポ良く覚えました。
特に例文モードを使うと「知ってる単語なのに読めない」という弱点を解消でき、リーディング力が安定しました。
問題ごとに音声を聞いて、シャドーイングしたことで、リスニング力も同時に身につけられました。
長文でシャドーイングが高校生の頃から苦手で、効果はあると知ってたけど自分には向かないと思っていました。
アプリだと単語の問題集からチャンクだけで挑戦できるのも良かった。
TOEICだと有名な金フレは、mikanだと例文で出題も選べて、
単語を解いて間違ったものだけシャドーイングできるので、苦手なものだけ集中して少しずつ取り組むことができました。
チャンクで聞くし、発音するので、徐々に文章が聞き取りやすくなったし、長文のシャドーイングもできるようになりました。
前からmikanは良かったけど、ここ数年でコンテンツ充実してて絶対使ってほしいです。
GoodNotesで誤答ログを残して復習導線を作る

TOEIC対策開始のタイミングでスケジュール管理から各種勉強用のノートをGoodNotesに切り替えました。
スケジュール管理をデジタルノートにしたことでタイパがかなり上がったし、仕事との両立も無理なくできました。これ、革命!
mikanで間違えた問題や公式問題集で落とした問題は、すぐにGoodNotesにまとめました。
タグを付けて整理しておくと、後から「#文法」「#Part7」などで検索できて便利。
ノートに書き込むときは、矢印・囲み・色分けを使って「自分の理解が引っかかったポイント」を残すようにしています。
これで弱点がどこか一目で分かるマイ問題集ができあがりました。
iPad+ペンシルが学習効率を変えた理由

GoodNotesもmikanも基本的にiPadで使っています。
私は紙のノートよりも、iPad+ペンシルで学習を一元化したことで本当にラクになりました。
(それまでは特に何か学ぶときは、無印のA3の方眼ルーズリーフを横でまとめたり、問題解くのに使っていました。)
タブレットは持ち運びしやすいので、移動中やカフェでもすぐに復習できるし、
手書き・スクショ・検索が1つにまとまります。
問題集とノートを持って出かけなくてもタブレットさえあればすぐに勉強開始できるし、他の仕事の書き物系も全てデジタルノートにしたのでタブレット自体は重さはありますが、いろんなノートや問題集などを持たなくて済むようになったので、結果的に荷物が減りました。
「勉強環境を整える」というより、生活の中に勉強を組み込む感覚になり、続けやすかったです。
私が使っているiPadとペンシルはこちらです。
最新でなくても純正ペンでなくてもデジタルノートやTOEICの勉強にはとりあえず十分でした。
2パターンで使えるケースもおすすめ。
この3つ(mikan,iPad,ペンシル)を組み合わせたことで、短時間の学習でもムダがなくなり、スコアアップのスピードが一気に加速しました。
次は、これらをどうやって週ごとのルーティンに落とし込んだかを紹介します。
スポンサーリンク
週ごとの勉強ルーティンと復習サイクル

スケジュールの設定はちょっと時間かけました。
なので、シェア!どんどん使ってください。カスタマイズ方法も紹介するよ
「限られた時間をどう配分するか?」が一番悩むポイントだと思います。
私が実際にやって効果があったのは、平日=積み重ね、週末=強化と分析というサイクルです。
平日(30分〜1時間):毎日の積み重ね

平日、全然時間ないけど、1時間ならどうにかなる!
平日は仕事や学校があるので、まとまった時間は取りにくいですよね。
私は始業前や休憩のスキマ時間にmikanを使い、単語・文法・例文をテンポよく復習しました。
夜は15~30分ほど公式問題集の単語や文法、リスニングの問題を解き、間違えた部分をすぐにスクショしてGoodNotesに保存しました。
平日は「解くこと」「間違えを記録すること」に徹し、考え込まないで次へ進むのがポイントです。
疲れた日は次の日に少し多めにするか週末に回すということで適度にやらない日もありました。
気持ちは焦るんですが、それがさらにその時間で覚えきろうという気持ちに拍車をかけました。気合。
週末(3〜6時間):復習+集中力トレーニング

ご褒美のランチとか用意して、午前中で終わらせるとか、日曜遊ぶために土曜日に一気にやるとかメリハリを。
受験生じゃないから、付き合いは断らないし、ご褒美はたっぷり。
週末は3~6時間を確保して、平日に間違えた問題を#文法 #リスニング #Part7といったタグごとに復習しました。
特にリーディングは時間を計って演習し、解答の根拠をノートに書き込むことで理解が深まりました。
ここで重要なのは、「耐久力」と「復習精度」を上げること。<br>
TOEICは2時間集中し続ける試験なので、週末に意識して長時間演習を入れると本番に強くなります。
GoodNotesとmikanをリンクさせた復習フロー

週末に何するかは大事!
この仕組みを作っておくと、「復習のために何をやるか」でも迷わなくなり、自然と繰り返し学習ができました。
平日に思いついたこと、もしかしてこれも苦手かも?とか手応えとかも走り書きしておくと、その感触がGPTに伝わるので、伴走してもらえます。
この週ごとのルーティンを回すことで、学習が「やりっぱなし」から「積み重ね」に変わり、スコアアップにつながりました。
GoodNotes+ChatGPTで弱点分析をする方法(プロンプト)

AIが出てきたからできる勉強法です。タイパがすごく上がりました。
本来なら個別指導でやってもらうことをAIにしてもらうことで、最短で点数を上げられました。
週末はただ解き直すだけではなく、GoodNotesにためた誤答データを活用しました。
タグごとにまとめたページをエクスポートしてChatGPTに渡すと、自分の弱点の傾向や優先して克服すべき範囲を分析できます。
これにより「なんとなく復習する」から「点数につながる復習」に変わり、効率が一気に上がりました。
この週ごとのルーティンを回すことで、学習が「やりっぱなし」から「積み重ねと改善」に変わり、スコアアップにつながりました。
TOEICのスコアを短期で底上げするため、今週の誤答データ(PDF)から
①弱点の可視化 ②優先順位づけ ③次の1週間の実行プラン を作ってください。
私は「週10時間」の学習時間で運用しています
【前提と希望】
- 目標:2ヶ月で900に近づける(現在は約○○点、計画実行⚪︎週目)
- 次回受験日:⚪︎/⚪︎
- 学習時間:今週は合計10時間(例:平日1h×5、週末2.5h×2)
- ツール:mikan(単語/文法/例文)、GoodNotes(誤答ログ)、公式問題集、必要に応じてUdemy
- 強み/弱み(自己申告):例)語彙は得意、Part7の速度と根拠把握が遅い、Part3-4の先読みが弱い
- 前週の弱点と対策:例)Part5で品詞問題を落とした → mikanで品詞問題を50問追加練習 → 正答率は改善。ただし時間はまだ遅い。
【入力データ】
- 添付PDFは、GoodNotesから出力した「今週の誤答ログ」です。
- タグの意味:
#文法(Part5)/#語彙/#リスニング(Part2-4)/#Part6/#Part7/#弱点=再発しやすいもの
【出力フォーマット(この順番・この見出しでお願いします)】
0) 前週の対策レビュー(2〜3行)
- 前回示した改善点が克服できているか?
- 新たに浮き彫りになった課題は何か?
1) 今週の弱点サマリー(3〜5行)
- 再発パターン(例:単数/複数、接続詞/前置詞、設問根拠の見落とし 等)
- 失点に直結している原因の仮説
2) 優先順位(高→低の3段階)
- High:今週必ず対処(理由も1行)
- Mid:来週に回しても良い(理由)
- Low:今回は触れない(理由)
3) 1週間の学習計画(合計10時間に収まるよう配分)
- 平日(各1h×5):mikanの具体リスト/Part別ドリル/短時間リスニング(先読み含む)
- 週末(各2.5h×2):1時間耐久リスニング/Part7時間計測/タグ別の誤答復習
- 使う教材・ユニット名を具体化(例:「公式問題集○○ Test2 Part7 Q147-175」)
4) 演習のやり方(各パートの手順を短く箇条書き)
- 例:Part7=設問→根拠線引き→根拠の言い換え確認→解答/時間超過時の打ち切り基準
5) 今週のチェックポイント(数値・行動指標)
- 例:Part3-4の先読み成功率、Part7の1パッセージ平均時間、文法の正答率 等
6) よくあるミスの回避メモ(1行Tipsを5つ)
- 例:受動/能動の見落とし、品詞の取り違え、設問の言い換えトラップ 等
7) 次週への引き継ぎ条件
- 例:今週の指標が未達なら、どのメニューを据え置くか/増減させるか
【トーン】
- 具体的・行動可能・数値で測れる提案にしてください。
- 一度にやり過ぎないよう、時間配分は厳守。優先順位の理由を必ず明記。
このプロンプトをテンプレ化しておくと、毎週「PDF添付→貼り付け→実行」で回せます。
私の場合は、返ってきた計画をそのままGoodNotesの週次ページに貼り付けて、チェックボックス化しています。
次は、学習を続けるために欠かせなかった集中力を保つ学習環境づくりについて紹介します。
スポンサーリンク
集中力を保つ学習環境づくり

TOEICの鍵は集中力の維持です!頭の良さとかじゃない。
TOEICは2時間の集中力が求められる試験です。
知識があっても、集中が切れてケアレスミスが増えるとスコアは伸びません。
私が実際に環境を整えてみて効果があったのは、「視線・姿勢・時間管理」を工夫することでした。
ブックスタンドで目線を上げる

地味だけど、すごく大事でした。
机にテキストをベタ置きすると、姿勢が崩れて首や肩が疲れやすくなります。
ブックスタンドを使って目線を上げると、長時間でも疲れにくく、模試を解くときの集中持続時間が変わりました。
このブックスタンドのクリアを使っているんですが、机に置いても向こう側が見えるので邪魔になりません。
家で勉強するときはこのブックスタンドにiPad載せてます。
リストレストで手首の負担を減らす

徹底的にストレス減らしていきましょう
iPadに手書きを続けていると、意外と手首や腕、肘が疲れて集中が途切れることがあります。
リストレストを使うと書く姿勢が安定して、長時間でも疲れにくい。
特に模試の復習でノートに大量に書き込むときに効果を実感しました。
タイマーで「試験時間」を意識する
リーディングで点を落とす原因の多くは「時間配分ミス」です。
私は勉強中からポモドーロタイマーを使って25分単位で演習→5分休憩を繰り返しました。
試験時間分はポモドーロタイマーで対応できなかったのでスマホタイマー使いましたが、
スマホのタイマーは地味に時間を食うので、普段の勉強は一度ポモドーロタイマー使ったら戻れないです。
毎日のことだし、他の仕事をやる時にもタイパ上がったのでちょっと高いけどおすすめ。

短期間で結果を出すために身体的なストレスや細々したロスを減らしました
こうして環境を整えたことで、学習のリズムが安定し、週10時間でも内容が濃い学習ができました。
次は、実際に2ヶ月間でどのようにスコアが変化したかを振り返ります。
最後の仕上げ|模試と講座で弱点を埋める

仕上げも大事。
2ヶ月の学習を積み重ねたら、最後は模試と講座で弱点をつぶすフェーズに入ります。
ここでは「本番シミュレーション」「効率的な補強」「直前の調整」の3ステップを意識しました。
公式問題集を使った本番シミュレーション
仕上げは公式TOEIC Listening & Reading 問題集を使います。
実際のテストと同じフォーマット・難易度なので、本番を想定した2時間通し演習を行いました。
演習後はGoodNotesに答え合わせと解説を書き込み、週末にChatGPTで弱点分析を依頼する流れを続けることで、直前まで改善ポイントが見えやすくなります。
Udemy動画講座でPart7とリスニングの型を学ぶ

Udemyは初回時に割引や季節ごとにセールやタイムセールをやっているので、こまめにチェックして直前で使えるようにしておきました。
短期間でスコアを上げたいときに有効だったのが、UdemyのTOEIC対策講座です。
特にPart7の長文読解の解き方や、リスニングの先読み・集中法は、独学では気づきにくいポイントが多いです。
スキマ時間に動画で解法パターンを学んでおくと、模試での点数が安定しました。
Udemyは季節ごとのセールや、初回登録時のタイムセールなどが狙い目です。
今後見る可能性が高いものはセール時に押さえておきましょう。
\夏のビッグセール! 明日の仕事に役立つスキルを学ぼう/
\対象コースが最大95%OFF/
試験直前1週間の過ごし方

総復習の方法教えるよ!
最後の1週間は新しいことに手を出さず、これまでやったことの総復習に徹しました。
・ GoodNotesにまとめた誤答ノートをざっと見直す
・ 公式問題集を1セット解いて時間感覚を確認する
・ リスニングは1日15分でも耳を慣らすことを継続
直前期は「焦って新しいことを詰め込む」のが一番危険です。
「やったことを信じて、落ち着いて試験に向かう」ことがスコアにつながりました。
ここまでで学習サイクルは完成です。
次は、実際にこの方法でどんな成果が出たのかをまとめます。
TOEIC900達成でわかった、効率重視の学習の本質

効率です、効率!
2ヶ月間、週10時間のペースで学習を続けた結果、私はTOEICスコアを約200点アップさせ、900点を取ることができました。
決して一日中勉強できたわけではなく、むしろ「時間が限られていたからこそ」効率を徹底する必要があったと思います。
成果のポイント

成果を出せたポイントまとめです
やってみて感じたこと
短期間でスコアを上げたいなら、勉強時間を増やすよりも復習の質を高めることが大切です。
そして「AIに分析を任せる」「ノートを一元化する」といった仕組みを作っておくと、迷わずに学習が進められます。
これは英語学習だけでなく、他の資格試験や仕事のスキルアップにも応用できると感じました。
これから挑戦する方へ
もしあなたが「時間がない」「やっても伸びない」と感じているなら、まずは今回紹介した学習サイクルを1週間だけ試してみてください。
小さな積み重ねと復習の仕組みが習慣になると、自然にスコアアップが見えてきます。
「正しい方法で積み重ねれば、2ヶ月でも十分に結果は出せる」
私自身が体験して強くそう思います。
あなたの学習が成果につながるように、ぜひ今回の方法を役立ててみてください。
TOEIC900達成でわかった、効率重視の学習の本質

勉強時間は目安、自分の苦手を徹底的に克服する問題を解いたり、集中力を身につけることが重要です。
2ヶ月間の挑戦を通じて感じたのは、「勉強時間」よりも「勉強の質」をどう作るかがすべてだということです。
短期間で伸びる人の共通点
塾講師時代に、英検や大学入学前のTOEICの指導もしていました。
その時のことも踏まえると、伸びる人にはこんな共通点がありました。
間違えた問題を必ず「見える化」して復習に活かしている
単語や文法はアプリなどで効率化し、暗記を作業化(ルーティーン化)している
模試や講座で「本番の型」を身につけている
学習環境を整え、集中力を2時間維持できる準備をしている
「やる気が続かない」「効率よくやれない」と悩んでいた私でも、仕組みを整えたことで学習が自然に続くサイクルになりました。
特に、GoodNotes+ChatGPTで誤答を分析する流れは、復習の“質”を大きく変えてくれました。
次に挑戦するあなたへ

TOEICは英語の才能じゃないです。誰でも高得点は狙えます!
TOEIC900は「特別な才能がある人だけの目標」ではありません。
限られた時間の中で、正しい方法とツールを組み合わせれば、2ヶ月でも結果は出せます。
まずはアプリやノートを整えて、1週間だけでも試してみてください。きっと「勉強が回る感覚」が掴めるはずです。
効率的に積み重ねれば、あなたもTOEIC900は現実になります。
ぜひ今日からスタートしてみてください!